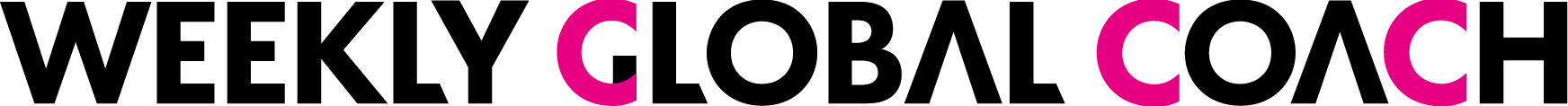バーンアウト(燃え尽き)の時代に、「働く意味」をいかに創れるか
~「フィードバック」の持つ力を再考する~
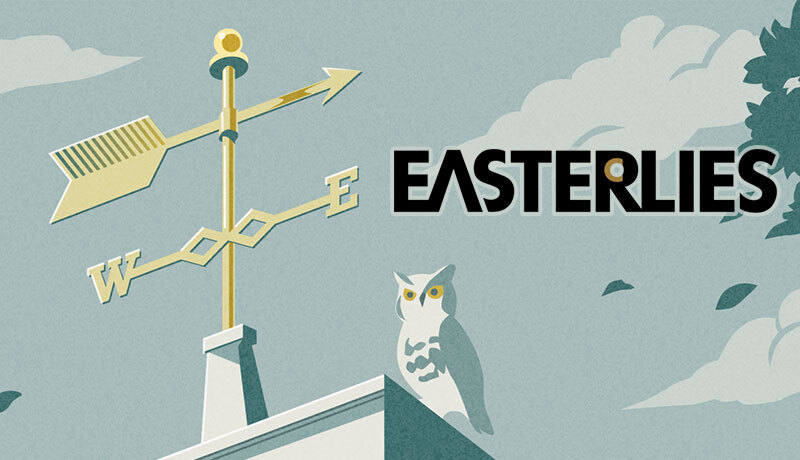
2022年、Microsoftの調査では、マネージャーの53%が職場でバーンアウト(燃え尽き)を感じていると報告され(※1)、多くの人に衝撃を与えました。バーンアウトが進行すると、判断力や創造性が低下し、生産性にも影響が出ます。Gallup社の試算では、バーンアウトの重大な兆候である「従業員エンゲージメントの低下」により、世界全体で年間8.8兆ドル(GDPの約9%)もの経済損失が生じているとされます(※2)。
「バーンアウト」と聞くと、過密スケジュールに追われ、責任に押しつぶされる“多忙な人”を思い浮かべがちですが、それだけではありません。米ハーバード・ビジネス・レビューの記事「Is Your Burnout From Too Much Work or Too Little Impact?(あなたの燃え尽き症候群は、“働きすぎ”が原因?それとも、“手応えのなさ”が原因?)」では、バーンアウトの原因は必ずしも「仕事の多さ」ではなく「仕事に意味や手応えが感じられないこと」にあることの方が多いと指摘されています。人はただの“作業者”になるのではなく、「意味ある貢献がしたい」と願う存在だからです。
今回は、この“働く意味の喪失”という観点からバーンアウトの本質に迫り、組織のリーダーがどうすれば「意味ある職場」を築けるのかを探っていきます。
バーンアウトとは
そもそもバーンアウトとは、「意欲的に働いていた人が、急に燃え尽きたように働かなくなる、または、働くのを厭うようになること」を指す。症状としては、心身が疲弊し、他者への思いやりや共感が薄れ、無力感や自己嫌悪に陥ってしまう。
前述のとおり、バーンアウトは単なる「働きすぎ」だけが原因ではない。バーンアウトには、以下の3つのタイプがあるとされている(※3)。
① 過負荷型バーンアウト(Overload Burnout)
バーンアウトの最も一般的なタイプ。仕事への情熱が強く、責任感の強い人に起こりがちで、成功を追い求め、健康や私生活を犠牲にして働き続けることによって起こる。
② 刺激不足型バーンアウト(Under-Challenged Burnout)
仕事が単調すぎたり、評価や成長の実感が得られないことで生じる。次第にやる気を失い、無気力になる。皮肉や現実逃避、思考停止など、回避的な態度が目立つようになる。
③ 放置型バーンアウト(Neglect Burnout)
周囲からの指示やサポートが不十分で、自分の努力が報われないと感じるときに起こる。自信を失い、苛立ちや不安が募り、行動・挑戦の意欲が失われ、「どうせ何をしても無駄だ」と感じるようになる(「学習性無力感」)。
②や③のように、バーンアウトは刺激や挑戦の不足、あるいは十分なサポートが得られないことによっても引き起こされる。上記3つのタイプに共通しているのは、「自分は役に立っている」「成長できている」「努力が認められている」といった実感――すなわち“効力感”の喪失ではないだろうか。冒頭で触れたとおり、バーンアウトの根底には、「自分の仕事に意味や手応えを感じられない」という深い孤独感や虚無感が潜んでいるのだ。
社員は仕事に“意味”を求めている
実際、求人サイトMonsterの調査では、Z世代の約75%が、基本的な職務ニーズ(例:公正な給与、安全な労働条件)が満たされてさえいれば、「給料よりも、仕事の意味・目的の方が重要」と回答している(※4)という事実がある。さらに、従業員の約80%が「給料が20%上がること」よりも、「仕事の意味を与えてくれる上司」を望んでいるのだという(※4)
こうした調査結果は、私たちが今、「ただ働く」のではなく、「意味を感じながら働く」ことを、これまで以上に重視している時代に生きていることを示している。実際、仕事に意味ややりがいを見出している人ほど、生産性が高く、離職率が低く、仕事満足度も高いという研究結果もある(※4)。しかし、冒頭で見た多くの社員がバーンアウトを経験している現実は、いまの組織が、社員が本当に求めている“意味”を十分に創れていないことの表れなのかもしれない。
では、人はどのようなときに、仕事に意味を見出すことができるのだろうか。
専門職を対象に行われた調査では、「仕事の挑戦レベル」と「満足度」に明確な相関があることが明らかになっている(※5)。人は、「やや難しいが、頑張ればできそうな仕事」にこそ、最も意味を感じるのだという。難しすぎれば挫折し、簡単すぎれば退屈になる。その中間の“ちょうどいい挑戦ゾーン(スイートスポット)”にある仕事こそが、社員に働く意味を感じさせ、燃え尽きを防ぐ鍵となる。
“意味”ある職場をつくるフィードバックの力
では、組織のリーダーはどのようにして、“意味”のある職場を創ることができるだろうか。
部下が“ちょうどいい挑戦”に取り組み、仕事に意味を見出すために最も重要なのは、上司からの「フィードバック」だ。これまで見てきたように、人は放置されたり、刺激がなさすぎたりすると、仕事に意味を見出せなくなってしまう。上司からの建設的なフィードバックは、単なる評価やアドバイスではない。自分の挑戦が適切な方向に向かっているか、自分の努力が誰かに届いているかを確認するための重要な手がかりとなり、部下の仕事の意味を支えることにつながる。
米ハーバード・ビジネス・レビューの記事「Why Feedback Can Make Work More Meaningful(フィードバックが仕事をより有意義にする理由)」では、フィードバックは①「熟達感(Mastery)」を育て、②「自分の影響力(Impact)」を実感させ、③「自分は見てもらえている」と感じさせる力があると紹介されている。たとえば、資料を作成した部下に「よくできたね」とだけ伝えるのではなく、「資料の構成がわかりやすく、クライアントの前向きな判断につながった」と具体的に伝えると、仕事の意味や自分の強みを実感することができる。また、部下が締切までに資料を送ってこないような場面でも、「資料がまだ送られてこないよ。なぜ遅れたの?」と責めるのではなく、「資料が届いてないけど、何か困っていることがある?」と伝えれば、相手は「自分と自分の仕事をちゃんと見てもらえている」と感じることができ、対話のきっかけにもなる。
心理学者のデイヴィッド・イエーガー氏とその研究チームは、このような前向きなフィードバックを「賢明なフィードバック(wise feedback)」と呼んでいる。彼らの実験研究によると、①自分の可能性を信じてくれる、②強みを思い出させてくれる、③支援を申し出てくれる、④信頼関係を築いた上で改善点を伝えてくれる——こうした相手からのフィードバックを、人はより前向きに受け止め、改善に取り組む傾向があるという。
現代は「個性や価値観の尊重」が重要視される時代であり、フィードバックのように相手に踏み込む行為に対して私たちが躊躇を感じる場面も少なくない。ただ、相手の個性や価値観を「尊重」することと、踏み込まずに距離を置いたり、「無関心」を装ったりすることは似て非なるものだ。相手の尊厳を守りながら、その成長や可能性に寄り添う姿勢が、今のリーダーに求められているのではないだろうか。
精神分析家スティーブン・グロスはこう語る。
「人が本当に欲しているのは称賛ではなく、“自分のことを真剣に考えてくれている”という感覚だ」
フィードバックとは、まさにその実感を届ける手段であり、“意味ある職場”をつくるための、小さくも確かな一歩なのだ。
Q:今、あなたの職場で「意味」は感じられているだろうか?それはなぜだろうか?
Q:過去に、あなたに「意味」を感じさせてくれたフィードバックには、どのようなものがあるだろうか?
Q:あなたのチームや組織に「意味」をもたらすために、他にあなたができることは何だろうか
(記事執筆:コーチ・エィ 椎根小稀)
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考文献】
※1 https://hbr.org/2023/05/more-than-50-of-managers-feel-burned-out
※2 https://hbr.org/2024/04/how-burnout-became-normal-and-how-to-push-back-against-it
※3 https://hbr.org/2022/08/3-types-of-burnout-and-how-to-overcome-them
※4 https://hbr.org/2025/01/why-feedback-can-make-work-more-meaningful
※5 https://hbr.org/2021/12/is-your-burnout-from-too-much-work-or-too-little-impact
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。