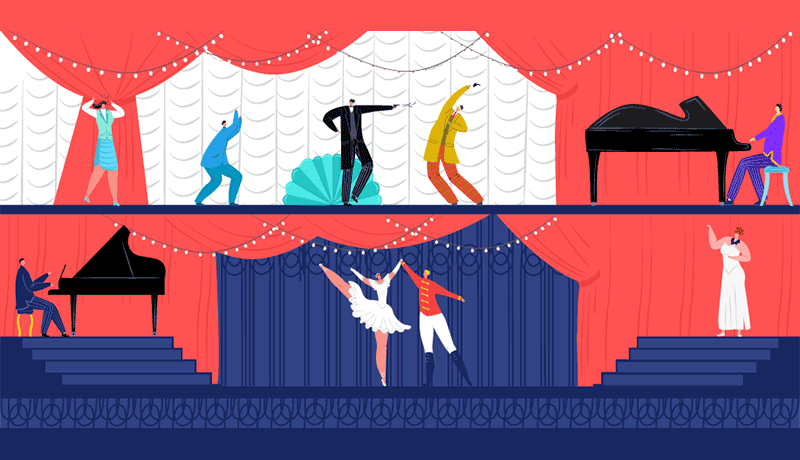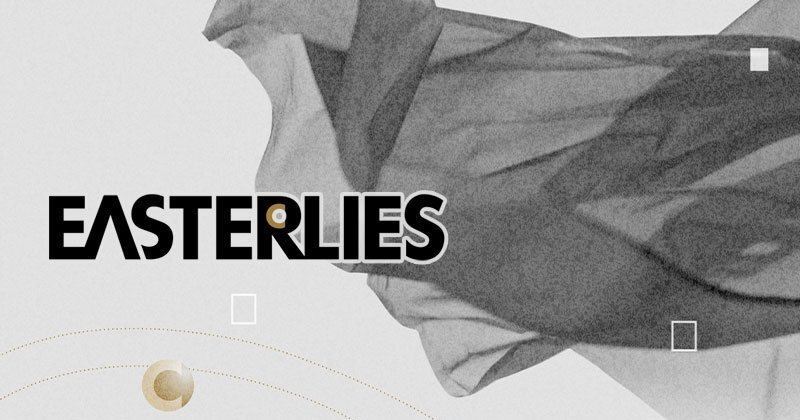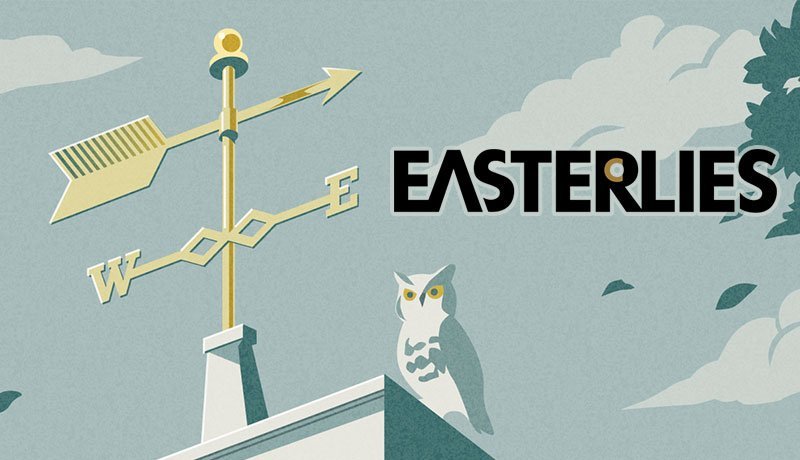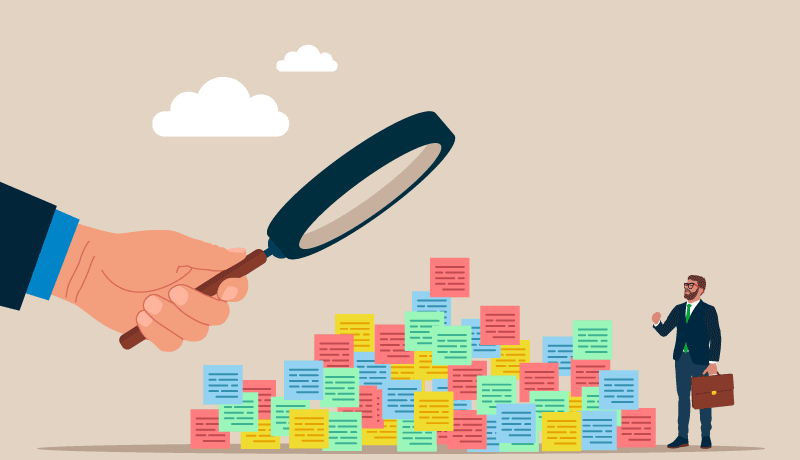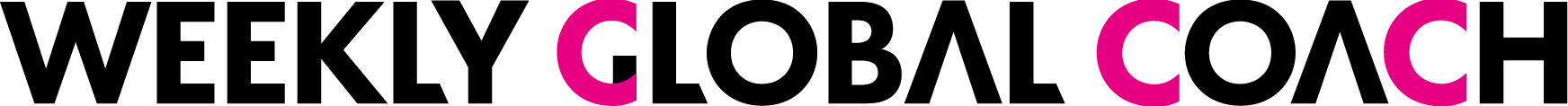Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
「かわいい私には旅をさせろ
~ 異なる価値観が主体性を目覚めさせる」

最近、「自分とは異なる価値観」と真剣に向き合ったのは、いつだったでしょうか?
異なる宗教、異なる文化、異なる生活習慣など、あなたの「当たり前」が揺らいだ瞬間に、何が起こりましたか?
主体性のあり方への問い
先日、出張でアメリカに2か月ほど滞在し、途中立ち寄ったヘアサロンで、現地の美容師さんから不意にこんなことを聞かれました。
「ねえ、日本って、なんであんなに投票率が低いの?人任せにするの、怖くない?」
思わず言葉に詰まりました。「いやいや、そんなことは……」と答えつつも、内心ドキッとしました。
ちょうどその頃、アメリカではトランプ大統領による軍事パレードへの抗議デモが全米各地で起こり、約600万人がデモに参加。私が滞在していた街でも、現地スタッフからはホテルから出ないように言われました。そんな後だったからこそ、美容師の問いが強く胸に残りました。
調べてみると、たしかに世界と比べた日本の投票率は低く、先月の参院選でも58.5%。一方、オーストラリアやドイツ、ベルギーでは80~90%超、アメリカも70%前後です(制度の違いはありますが)(※1)。この違いは単なる制度や文化の差ではなく、「社会に当事者として関わる意識」が、日本では相対的に低いことを示しているように感じます。単なる投票率の問題ではなく、私たち自身の「主体性のあり方」に深く関わっているのではないかと。
企業の現場にも、その傾向は見て取れるように思います。
弊社のリサーチによると(※2)、日本では「部下が上司に求める資質」として、「決断力」や「明確な指示」が他国よりも高く評価される傾向があります。つまり、「上司が決めてくれれば、私はその通りにがんばります!」という「受け身の主体性」が根付いている。これは、滅私奉公的で組織人としての美徳のようにも思えますが、裏を返せば「お上の仰せのままに」つき従う社員が増え、「自分で考え、行動すること」を避けがちになるリスクもはらんでいるとも言えます。
こうした「主体性」が欠如しているかのような現象は、日本人、日本の企業全体に蔓延しているのでしょうか。それに対する打ち手はあるのでしょうか。
海外赴任した若手が帰国後に感じる葛藤
アメリカでクライアント企業訪問を重ねるなかで、ある日系大手メーカー米国法人CEOのSさんから、印象的な話を伺いました。
「海外に赴任した若手社員は、帰国後には驚くほど主体的になります。でも、その変化を定着させるには、数年かかります」と。
同社では、海外赴任中、日本人社員をリエゾン(橋渡し)的な“安全地帯”には置かず、現地ビジネスの最前線に放り込み、現地のマネジメントラインの中に入れるそうです。そこで、彼らは現地社員とぶつかり、異なる価値観に直に触れながら、自分なりの判断や意思決定を求められていきます。それは自分がそれまで持っていた「当たり前」を自分自身から解き放っていくプロセスであり、成功も失敗も貴重な材料になります。ところが、日本に戻ると、日本の会社の空気や慣習、日本独特の同調圧力などに飲みこまれ、もどかしさを感じながら、元の「受け身の主体性」に戻ってしまうことも少なくない。
その「もどかしさを感じている時間」こそが、真の主体性が内側から育つために必要なプロセスなのだと、Sさんは語っていました。帰任した社員が再び壁に直面するとき、海外での経験と日本での同調圧力、日本文化との葛藤、衝突が内面で起こるわけです。そのとき、上司がそのプロセスにどう関わっていくか。上司や周囲の支援のあり方が、本人の変化を一過性で終わらせるか、定着・深化させるかの鍵を握っているのだそうです。
発酵の時間を醸成する対話の力
Sさんの会社では、そのもどかしさを感じている時間を「発酵の時間」と捉えているのだそうです。見た目に変化は表れなくても、内側で思考や感情が熟成していく。焦って火を入れれば台無しになる。焦らず、急かさず、そっと見守る。上司は、その沈黙や戸惑いの中にある“うねり”に耳を澄まし、言葉や伴走でそっと支える、そんな認識を上司が持つことが、部下の変容を本物にするカギだと。
具体的には、帰国した社員に対して、上司や社内コーチ達が「どうだった?」と成果を聞くだけでなく、
「何に違和感を持ったのか」
「何が自分にとって“正しさ”だと感じられたのか、それは今とどう違うのか?」
「今のあなたが、前よりも大事にしている「信念」はなにか」
といった、価値観の揺らぎに目を向けるような問いを投げかけるのだそうです。それは評価のための面談ではなく、内省と対話を通じて、内側にある主体性の種を芽吹かせるための時間になります。その「聞く力」こそが、帰国後の社員の変容を持続可能なものにする。まさに「発酵の時間」の醸成だと、Sさんは語っていました。
実際、ある若手社員は、帰任前後を振り返って「今までなら“前例踏襲でいいや”と思ってたけれど、今はそれが気持ち悪く感じる」と語ったそうです。
異文化での衝突や苦労を経て、「自分で考える」ことの本質的な意味に気づいたその社員は、組織の空気に流されそうになる自分を内側で踏みとどまろうとしていたのだと思います。
そのような「もどかしさ」の中にある部下の声を、どれだけ丁寧に受け止められるか。それが変容の本質を支える鍵だということだと。
最近では、パスポート保有率も下がり続け、異文化や多様性への接点がますます少なくなる中、日本の一部には、異質なものに対する拒絶反応が広がっている印象さえあります。しかし、異なる価値観に触れるというのは、外の世界を知るだけではなく、自分の「当たり前」そのものを自覚するということ。
自分の「外側」を知って初めて、自分の「内側」が見えてくる。そのときこそ、「自分はこうありたい」と語ることのできる、まさに主体性が芽生えるのではないでしょうか。
あなたは、自分の「当たり前」を揺さぶる旅を、最後にいつしましたか?
そして、その旅の記憶は、今、どこで息づいていますか?
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考資料】
※1 international IDEA(民主主義・選挙支援国際研究所)、世界の国・地域の議会選挙 投票率、2024~2025年7月17日
※2 コーチング研究所、「組織とリーダーに関するグローバル価値観調査」、2024年
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。