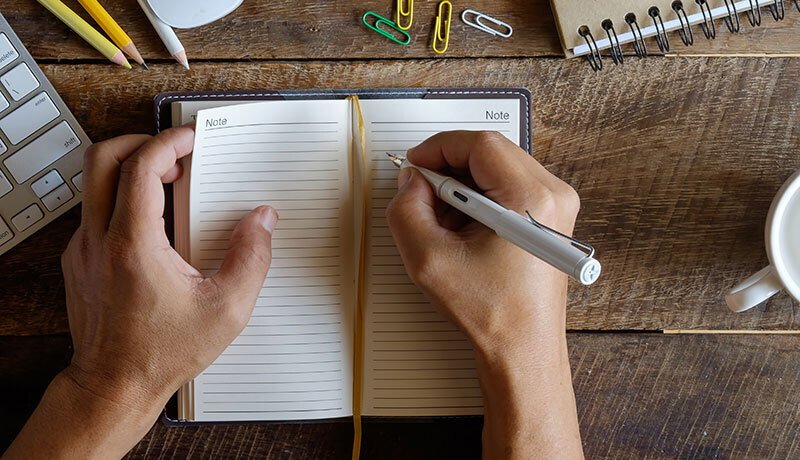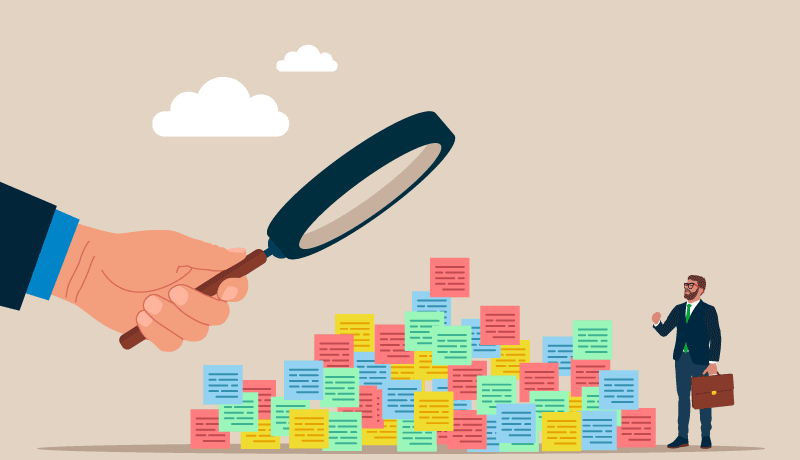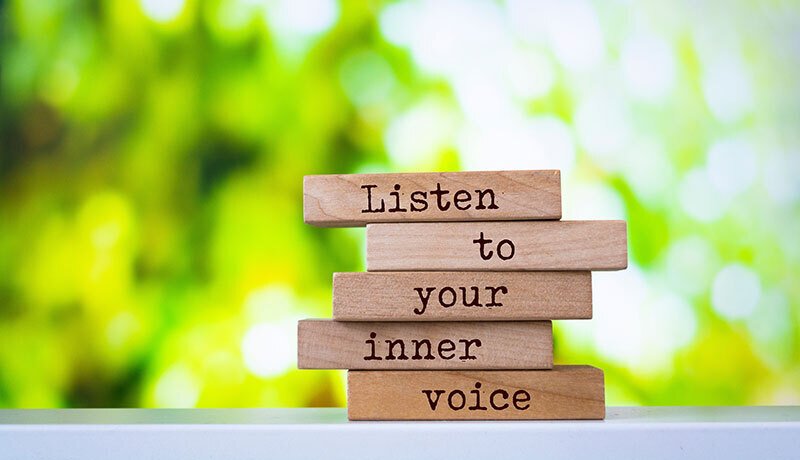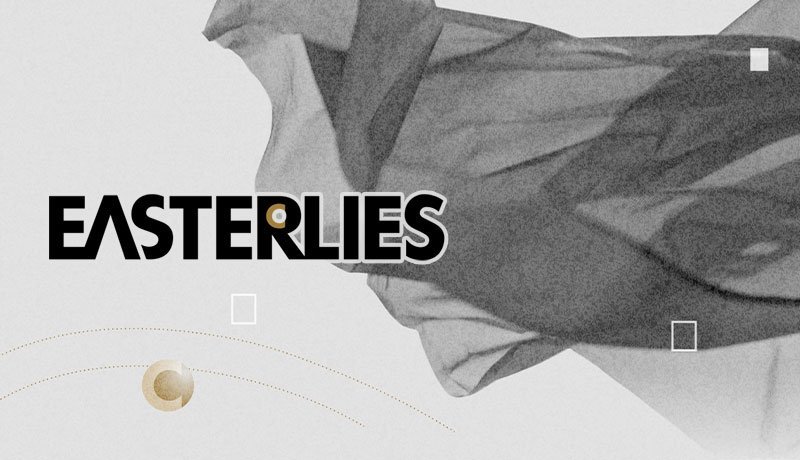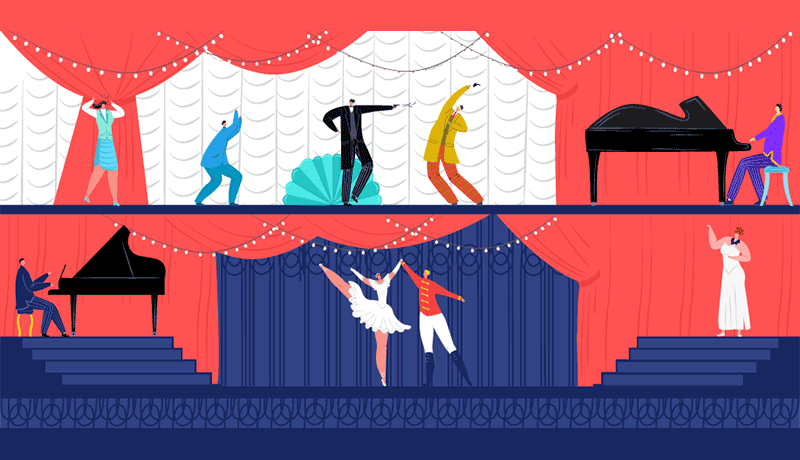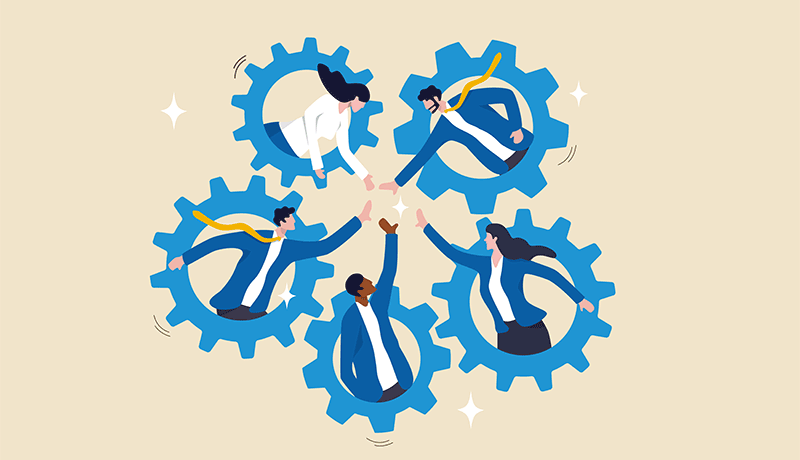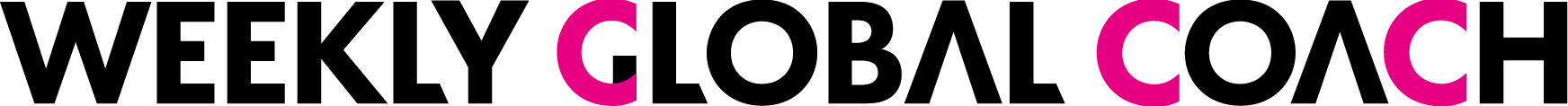「未完成」を力に変える—不確実な時代のリーダーシップ

2020年代、私たちを取り巻く環境はかつてないほど複雑化し、「正解のない問い」で満ちています。必然的にリーダーは、「すべてを知るリーダー」「答えを示し導くリーダー」という従来の像を手放さざるを得なくなっています。一方で、そんな複雑で不確実な状況だからこそ、人々はリーダーに「正解」や「導き」をますます期待しているという側面もあります。
この状況に対し、現代のリーダーはどこに拠り所を見出せるのでしょうか。ひとつの示唆を与えるのは、マイクロソフトCEOサティア・ナデラの回顧です。
彼は、自社文化を「know-it-all(何でも知っている)」から「learn-it-all(何でも学び続ける人)」へと転換させたことが企業再生の核心であったと語っています(※1)。この視点を手がかりに、今回のEasterliesでは「不確実な時代のリーダーシップ」の可能性を考えてみます。
正解のない中でのリーダーシップ
複雑で不確実な状況において、リーダーは「答えを出す存在」であることをますます求められている。しかし、そもそも個人の知識や経験の蓄積だけでは限界がある。むしろ、ソクラテスの「無知の知」のごとく、「答えを知らない」ことを認識することで初めて新たな地平が開けることの真価を今こそ見出すときではないだろうか。
「知らない」「わからない」に直面したとき、私たちは未知を探るべく「問い」を立て共有する。それは、知識を集めること以上に、人々を「共に考える状態」へと導く行為でもある。問いが発せられるとき、その場にいる人々は立ち止まり、問い直す余白が生まれる。その余白に多様な視点や声が流れ込み、物事のとらえ方、可能性、意思決定の幅が広がっていく。
この点からは、特に正解が存在しない課題に直面するリーダーや組織にとって、「問い」は「答え」以上に力を持つ。マイクロソフトのサティア・ナデラが語る「know-it-all(何でも知っている)」から「learn it all(何でも学ぶ)」への転換も、単に知識の拡張を意味するにとどまらず、未知を探る問いを立て続ける姿勢であるといえるのではないだろうか。
しかし、そのように問いを立て続けることは容易ではない。なぜなら、問いはしばしば自らの「知らなさ」をさらけ出すことに直結するからである。
「知らなさ」そして「脆弱性」を受け入れるという選択
リーダーが「知らない」「わからない」と口にするのは、決して容易なことではない。それはリーダーの立場や威信を揺るがし、他者の評価にさらされる瞬間でもある。加えて、未知に向き合う姿勢は「脆弱性」を引き受けることにも重なる。それは私たちに恥や恐怖を感じさせる。
この「脆弱性」にリーダーシップの観点から注目するのが、ヒューストン大学ソーシャルワーク大学院の研究者であるブレネー・ブラウン博士だ。ベストセラー作家でもある彼女は自著、『Dare to Lead』において、リーダーシップを「人やプロセスの中に可能性を見出す責任を負い、その可能性を伸ばす勇気を持つ人びとのことである」と定義した上で、脆弱性を示すことは弱さではなく「勇気」の表れであると強調。また、「脆さを見せるには信頼が必要であり、信頼を築くには脆さを見せる必要がある」と指摘し、この循環に伴うリスクを引き受けることこそ勇気あるリーダーの条件だと説く(※2)。
プロジェクトをうまく進められないとき。部下からのフィードバックが想定以上によくなかったとき。リーダーである自分も「知らない」「わからない」とき。そうした自らの「脆弱性」が露呈する経験は誰もが避けたいものだ。そうした脆さをリーダーが勇気を持って受け入れ、自らの限界を周囲と率直に共有するとき、そこには信頼に加え、協働や学習も芽生える可能性がある。また、完璧を装うのではなく、自分の限界や不足、いわば自らの「未完成さ」を隠さず周囲にも開いていくというリーダーのあり方は、関わる人にも伝播し、結果として職場のオープンネスや協働、ひいては組織の学びを加速させるはずである。
「未完成」が組織にもたらすもの
ここでもう少し「未完成」を受け入れることが組織にとってどのような意味を持つのかを考えてみよう。
近年注目されているデザイン思考における重要なプロセスに「プロトタイピング」がある。プロトタイプとは「原型」や「試作品」を意味するが、IDEOのデザイン思考においてプロトタイプは単なる未完成の「試作品」にとどまらず、学びを加速させるための重要な実践である(※3)。
試作品とはいえ、何かをつくるとなると私たちはその精度や完成度にこだわり先延ばしにしてしまいがちだ。しかし、IDEO創業者デイヴィッド・ケリーは「Fail faster to succeed sooner(より速く失敗することでより早く成功する)」(※4)と語る。
失敗を恐れず、むしろそれを学びや知の拡張の手がかりとすべく、「未完成」を資源として扱うこの姿勢は、不確実性が常態化する時代において一層、組織の適応力や持続的な成長を実現するしなやかな組織づくりのヒントとなりそうだ。
また「未完成を資源とする」姿勢は、組織の強靱性を培う契機ともなりえる。現に冒頭で紹介したナデラの下でのマイクロソフトは、「know-it-all(何でも知っている)」文化から「learn-it-all(何でも学ぶ)」文化への転換により、停滞から成長へ向かい、時価総額は10年足らずで3兆ドル規模に達した(※1)。「知らない」「わからない」と向き合い、脆弱性を受け入れること、そしてそうした「未完成さ」を認め活かそうとする姿勢は、謙虚さの表れにとどまらず、組織の学習・創造・成果を駆動する実証的手段となるのではないだろうか。
「未完成」を資源に
ここまで見てきたように、不足や課題と思われがちな「知らない/わからない」「脆弱性」は、向き合い方次第で、学習や協働、創造を生み出す力にもできる。さらに言うなら、「正解」や「完全」の追求は、不確実性が常態化する時代においてはむしろ硬直を招きかねない。
周囲と共に「未完成」を学びと協働の資源に転じるリーダーシップを発揮すること。そのために、問いを携えて進む姿勢こそが、不確実な時代を切りひらくリーダーシップの本質なのではないだろうか。
● あなたは今、「未完成」をどのくらい資源にできていますか?
● 自分の限界や脆弱性を、誰と共有し、どんな学びに変えていきますか?
● あなたが今いちばん取り組みたい「正解」のない問いは?
(記事執筆:コーチ・エィ 山田里紗)
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考文献】
※1 Mehta, S. (2024, March 3). Satya Nadella changed Microsoft’s culture: How leaders can learn – fast company. Satya Nadella’s 3-word description of Microsoft’s culture should inspire leaders to be learners. https://www.fastcompany.com/91133383/microsoft-ceo-satya-nadella-3-word-description-microsoft-culture-leadership
※2 Brené Brown, Dare to Lead: Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts., Random House, 2018.
※3 Wilkins, J. (2024, July). 7 principles to guide your prototyping. IDEO. https://www.ideo.com/journal/7-principles-to-guide-your-prototyping
※4 Brown, T. (2013, October 30). Why you should talk less and do more: Ideo: Design thinking. IDEO. https://designthinking.ideo.com/blog/why-you-should-talk-less-and-do-more
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。