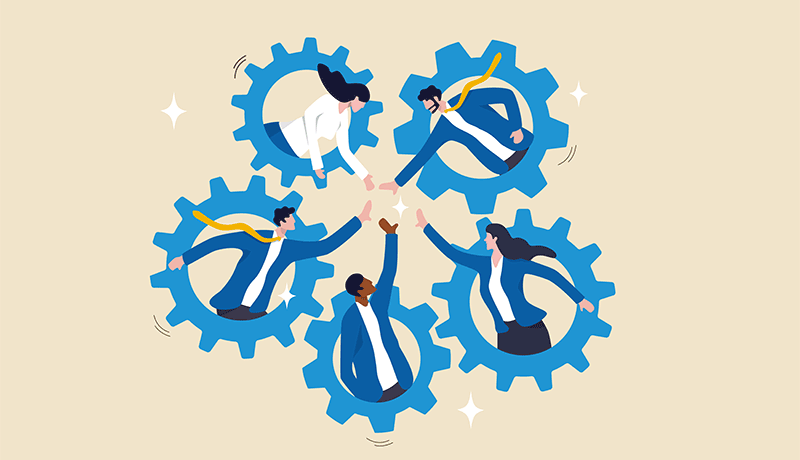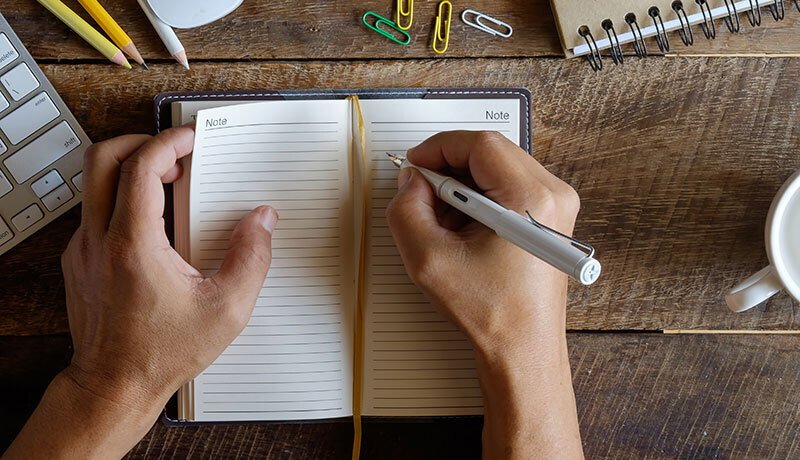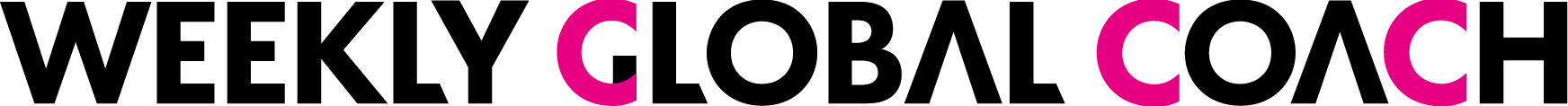言葉の貧困が阻むイノベーション 〜言葉を変えれば、未来が変わる~

企業の成長やイノベーションを推進する上で「言葉」の持つ力は見過ごせない要素です。
私たちは日々、言葉を使ってコミュニケーションをして、思考を深めています。一方で、慣れ親しんだ言葉を使い続けることで、思考が固定化され、新しいアイディアを生み出す力が低下することがあります。特に企業や組織において「どのような言葉を使うか」という日々の選択の一つひとつが、ビジネスに大きな影響を与えます。本稿では、言葉を見直すことや捉えなおすことがどのように企業の成長を促し、新たな可能性を切り拓くのかを考察します。
新しい言葉が次々と生まれる国
英語圏では、ビジネス領域における新語の創出が非常に活発である。たとえば、2024年にオックスフォード大学出版局が発表した「ブレイン・ロット(脳腐れ)」は、過度なSNS利用による悪影響を指す言葉として注目を集めた。また、2023年には米国のメリアム・ウェブスター辞典が690の新語を追加するなど、米国では年間数百もの新しい概念が生まれている(※1)。
特に米国のテクノロジー業界では「クラウドコンピューティング」「ビッグデータ」「メタバース」といった新語が登場することで、概念が広まり、議論が活性化し、新たな市場が形成されてきた。シリコンバレーのスタートアップでは「ピボット」「ムーンショット」「ハッカソン」といった新しい言葉が生まれ、それが企業文化そのものを進化させる原動力となっている。
このように、新しい言葉が生まれることは、企業や社会のイノベーションの推進力そのものを表しているともいえる。
言葉の貧困とは?
一方で、一部の国や組織では「言葉の貧困」が進行しているように思われる。
「言葉の貧困」とは、新たな概念や複雑な現象を適切に捉える語彙が不足している状態、あるいはごく限られた表現が過度に繰り返されることで、思考の柔軟性や創造性が失われている状態を指す。立教大学経営学部の中原教授は「言葉の貧困」が「実践の貧困」を招くと指摘している(※2)。
その極端な例として、パプアニューギニアのダニ族が挙げられる。彼らの言語には色を示す言葉が「明」と「暗」の2種類しか存在しないため、青と緑といった色の違いを視覚的に識別する能力が育ちにくいとされている(※3)。
では、日本はどうだろうか。
日本においては、ビジネスやテクノロジー分野における言語進化の速度が英語圏に比べて遅れがちであり「DX(デジタルトランスフォーメーション)」や「サステナビリティ」といった用語の多くが海外から輸入されている。しかし、それらの言葉が本来持つ概念的な深さや背景への理解が十分でないまま表層的に使用されるケースも少なくない。たとえば「DX」と「デジタル化」が混同され、単なるツールの導入や業務の電子化が「変革」と称される場面も散見される。
他にも、一部の言葉が過度に定着し繰り返し使いまわされることによって、組織全体の思考の柔軟性が失われているケースもある。たとえば「コンセンサス」や「ガバナンス」といった言葉が支配的な企業と「イノベーション」や「挑戦」といった言葉を中心に据える企業とでは、その組織文化や意思決定プロセスに大きな違いが生じることは想像に難くない。
このような現象は、言語学や認知心理学の領域においても理論的裏付けが存在する。言語学者ガイ・ドイッチャーは「使用される言葉の範囲が制限されると、思考の幅や創造性もまた制約を受ける可能性がある」と述べている(※4)。
言葉は思考を形づくり、さらには社会の構造や未来を方向づける力を持つ。言葉が貧しくなれば、思考もまた貧しくなり、やがて社会の創造性や多様性さえも損なわれる可能性がある。
現代社会においては、SNSなどのメディアを通じてバズワードが急速に拡散される。しかし、これらは本来の意味や背景を欠いたまま拡散されることが多いため、言葉の形骸化を進行させてしまっているともいえる。さらに、読書や対話といった深い言語的営為の機会が減少し、言語的視野の狭窄が進行している可能性も否定できない。
言葉の貧困を克服し、より豊かな社会を生み出すために、私たちは何ができるのだろうか。
企業は言葉をどう活用すべきか
ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーは「言語は存在の家である(言語は単なる道具ではなく、人間は言語の中にこそ生きている)」と述べたように、企業活動においても、言葉がその組織の未来を決定する(※5)。
企業がまず取り組むべきことは、単に独自の言葉を生み出そうとすることではなく、日常的に使われる言葉が、どのように組織の思考や行動を規定しているかを分析し、見直すことではないだろうか。たとえば「顧客志向」という言葉が根付いている企業では、優れたサービスを提供する一方で、顧客の要望に応え続けるあまり、単なる「御用聞き」になってしまう可能性がある。もし企業が顧客と共創するビジネスモデルを構築し、新たな価値を生み出したいのであれば「顧客志向」という言葉の枠を超え、新たな概念を示す言葉を選び直す必要がある。
このように、言葉の貧困は単なる表現の問題ではなく、企業の思考力そのものを制約する要因となり得る。これからの経営を司るリーダーには、単に戦略を策定するだけでなく、社内で使われる言語環境そのものを抜本的に変革する意識と覚悟が求められるのではないだろうか。
- あなたの組織の中で頻繁に使われている「常套句」は何か?
- この1年間、あなたやチームが生み出した新しい「言葉」は?
- あなた自身にはない視点や言葉を持っているのは誰だろうか?
(記事執筆:コーチ・エィ 宗像このみ)
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考文献】
※1 Merriam-Webster. We Added 690 New Words to the Dictionary for September 2023. Merriam-Webster, Sept. 2023.
※2 中原淳. 『「言葉の貧困」は「実践の貧困」を生み出す!?:実践を豊かにする「共通言語」をもつことの意味!?』 中原淳の研究室, 24 May 2022.
※3 今井むつみ(著)、『ことばと思考』、岩波書店、2022年
※4 Deutscher, Guy. Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages. Arrow Books, 2011.
※5 マルティン ハイデッガー(著)、渡邊二郎(翻訳)、『「ヒューマニズム」について』、筑摩書房、1997年
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。