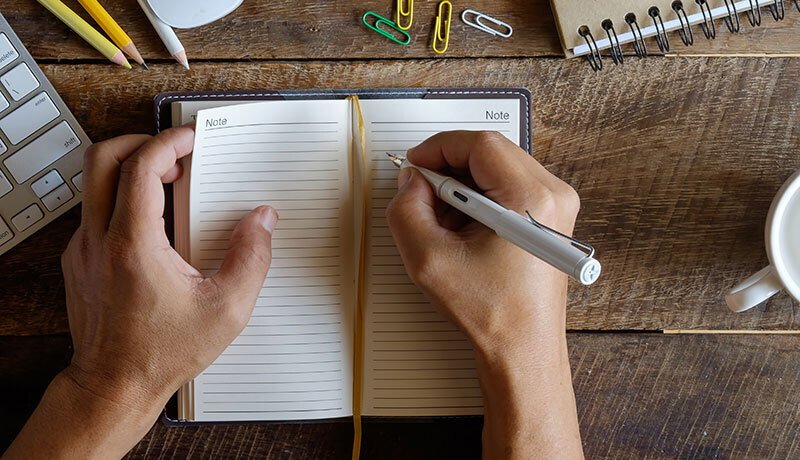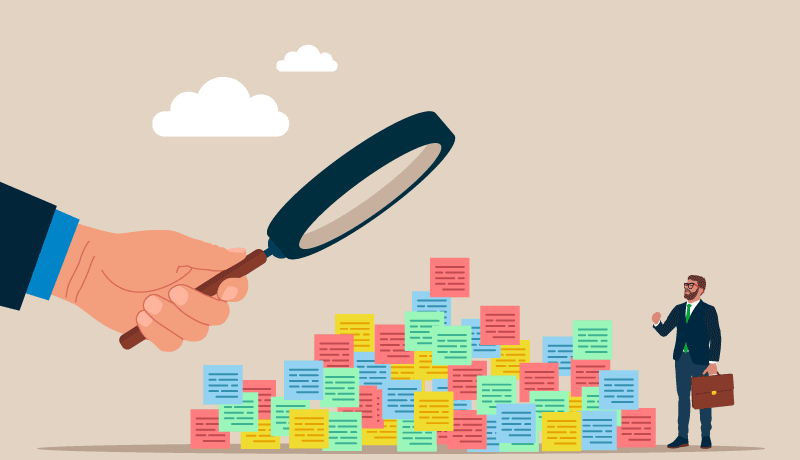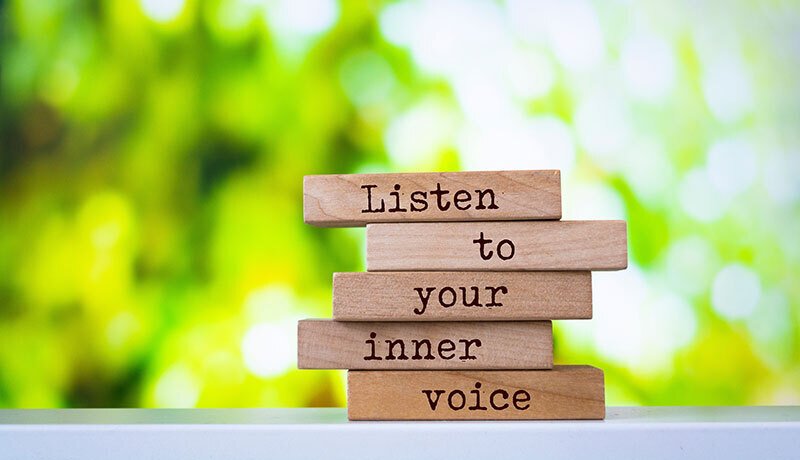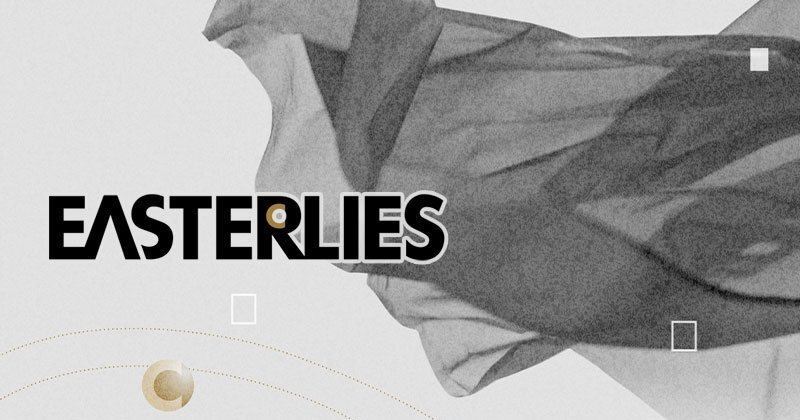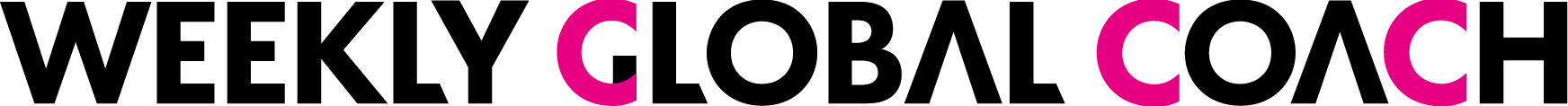Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
「心の状態」をつくる

コーチとして、リーダーとして、自分のハイパフォーマンス状態をどうつくれるのか?
今回は、チームコーチングの分野で世界的に有名なアレクサンダー・カイエ氏のトレーニングで学んだ知見を基に、このテーマについて探求してみます。
カイエ氏は、20年近いキャリアの中でコーチとして最も注力していることは、「自分の『心の状態』をつくることだ」、と話していました。動機の源は、自身の不安定な「心の状態」によって、同僚や最も大切な家族に深刻な悪影響を及ぼしてしまった反省にあるようでした(※1)。
私は、カイエ氏のトレーニングで不思議な体験をしました。
トレーニングは、複数人の経験豊かなトレーナーによって実施されました。誰もが聞き取りやすい英語で話していたのですが、なぜか、心に響く理解ができる方と、途中で理解ができなくなる方がいました。最初は単純に自身の英語力の問題だったり、分かりやすい単語の選び方かと思っていました。
しかし、ある時、話を聞いている私自身の「心の状態」が、どれだけ落ち着いているか、安心できているのか、そのことと私の理解力が連動しているように思えてきました。
「心の状態」がパフォーマンスに与える影響とは
カイエ氏は、「心の状態」を「私たちの思考と感情によって生み出される、人生における瞬間瞬間の経験」と定義しました。「0」を「心の状態」がニュートラルであるとしたとき、「+3~-3」の状態を表現する言葉を世界中で調査し、およその普遍性を発見しました。下記はその一例となります。
+3:歓喜、有頂天、恍惚な状態
+2:幸せな気持ち、やる気に満ちた、わくわくした状態
+1:満足している、穏やかな、静かに満たされた状態
-1:一杯一杯な、疲れている、不安な状態
-2:イライラしている、失望した、怒りを感じている状態
-3:切羽詰まった、絶望的で、希望が持てない状態
たとえば、今、皆さんの「心の状態」は、上記のどのスコアに近いでしょうか?
その状態は、あなた自身のパフォーマンス、周囲との人間関係に何をもたらす可能性があるでしょうか?
カイエ氏によると、最もパフォーマンスに好影響を与える心の状態は、「+1~+2」の時で、よりエネルギーが必要な時には、「+2」が望ましいようです。「+3」は、多くの場合良い影響を与えるのですが、ときに行き過ぎた決断などを引き起こすリスクがあるそうです。一方、「-1」の状態は、一時的であれば耐えられたり、優れたパフォーマンスのきっかけになり得るのですが、この状態が継続することはリスクであり、「-2~-3」は、重大な悪影響を及ぼす可能性が高い状態といってよいそうです。
「心の状態」の特徴とは
この「心の状態」には、いくつかの興味深い特徴があります。
まず、「世界の見え方」に影響を与えます。「心の状態」が「+2」の場合と「-2」の場合とでは、同じ状況が大きく違って見えます。確かに、気持ちがブルーな日には、楽しいはずのことも憂鬱に思えてしまいますね。
また、「心の状態」は、頻繁に変化します。誰でもマイナスの状態になりますし、多くの人が、短期間、時には数時間から数分のうちに、心の状態のレベルが上下動することを経験するようです。
そして、チームの中では、この「心の状態」が伝染しあう可能性があります。
トレーニングの中では、皆で頻繁に「心の状態」にスコアをつけて共有しあいました。最初、この取り組みが何のためなのか、不思議に思っていましたが、共有することで初めて、チームには「+1」の人もいれば「-2」の人もいる。そのことがはっきりと分かりました。
また、各人が自分の「心の状態」をスコアにすることは、自分の「心の状態」が自分のものであること、つまりそれを扱う責任が自分にあることを敢えて表明することになる、そんな効果があるように感じ始めました。こうして、チーム全員で、自らの「心の状態」を自らが引き受けること、自分と他者の「心の状態」の間に境界を認識することは、無用な感情の伝染をコントロールするために役立つかもしれません。
なお、トレーニングの最後に、必ず皆で自身の「心の状態」を共有しあったのですが、多くの人達のスコアは、幾分、上昇していることが殆どでした。これも、とても興味深い点でした。
そして、チームの中では、この「心の状態」が伝染しあう可能性があります。
「心の状態」を整えるアプローチ
さて、この「心の状態」は、意図して変えることはできるのでしょうか?
カイエ氏は、経験上、十分に可能であると言っていました。また、次に紹介するような統合的アプローチを習慣的に訓練することが有効であることを提案しています。
▽ステップ1:呼吸(共鳴呼吸)
10秒間の呼吸サイクル(吸気+ 呼気)を維持し、1分間に合計6回の呼吸サイクルを行います。
▽ステップ2:肯定的感情の再体験
感謝や愛情など、肯定的な感情を引き出す人や場所、物、体験を思い浮かべ、その感情を再体験します。
▽ステップ3:思考のリフレーム
自身に対して、1つの内省的な「What」の質問を投げかけます。
たとえば、下記のような「What」の質問は、思考のリフレーム(再構築)を誘いやすいでしょう。
・この状況において、もしチャンスがあるとすると何だろうか?
・今、自分の直感は、何と言っているのだろうか?
・この状況から、何を学べるのだろうか?
・今、ここで、本当に大切なことは何だろうか?
・この状況に対して、自分はどんな貢献を持ち込めるだろうか?
▽ステップ4:行動の選択
ステップ3で得た洞察を基に、小さく実現可能な、具体的行動を決めましょう。
たとえば、冷静に俯瞰できる「心の状態」に至ることで、「自身の主張への固執」から「他者の懸念に耳を傾ける」行動の選択が生まれるかもしれません。
また、「一歩ずつ、前進する」という行動の選択ができたとしたら、「圧倒される感覚」にあった「心の状態」の時とは、明らかな違いをつくれそうです。
「心の状態」とリーダーのあり方
ここまで「心の状態」という切り口で、リーダーとして、コーチとして、自らのハイパフォーマンスの基盤をつくり、周囲への影響を変えるヒントを探求してきました。最後に紹介した、「呼吸」→「肯定的感情の再体験」→「思考のリフレーム」→「行動の選択」の4ステップは、たった1分程度の時間で、「心の状態」に違いをつくることを可能にしますので、私は、機会がある度に練習をしています。また、「心の状態日記」も有効です。その日の「心の状態」をスコアで表現し、その状態を言葉にする練習になります。
私自身、過去に自分の「心の状態」に余裕がないことで、チームメンバーに不安を与えてしまった経験があり、リーダーシップは「今この瞬間」のあり方の積み重ねなのだと実感しています。日々、自分の「心の状態」と向き合い整えていくことは、リーダーとして、コーチとしての責任であり、実践でもあるのだと思います。
ご参考になれば幸いです。
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考資料】
※1 Insight Channel: ‘The Power of State of Mind’ with Alexander Caillet
※2 Alexander Caillet, Jeremy Hirshberg and Stefano Petti, “How Your State of Mind Affects Your Performance”, Harvard Business Review, December 8, 2014
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。