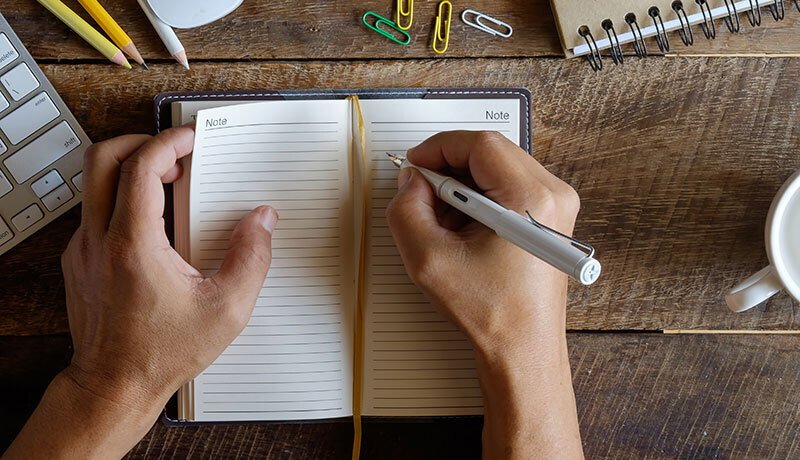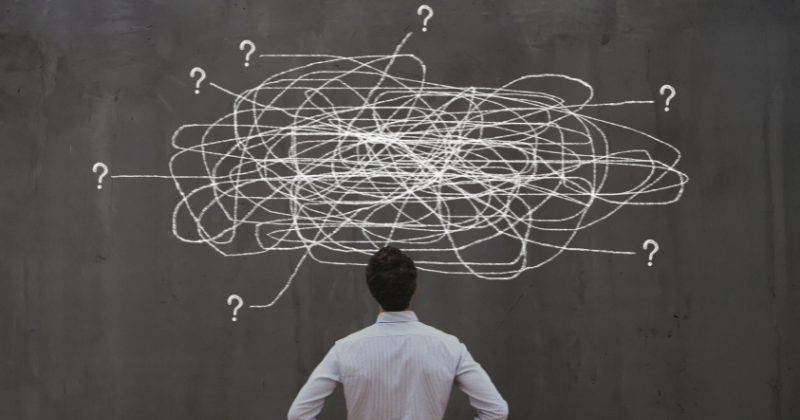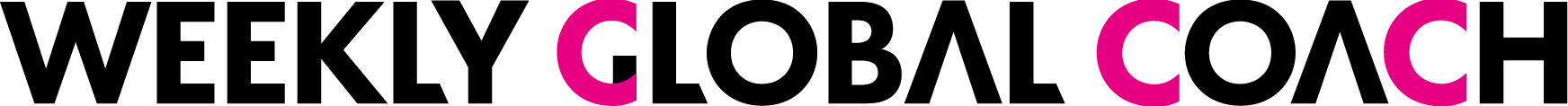Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
なぜ、次のリーダーを開発する人がリーダーなのか?

リーダーとはどういう存在のことをいうのでしょうか。
みなさんもそれぞれの経験や学習を通じた定義を何かしらお持ちだと思います。
コーチ・エィではリーダーの定義の一つとして、「次のリーダーを開発していること」をあげています。これはどういうことなのでしょうか。なぜ、次のリーダーを開発することがリーダーの定義なのでしょうか?
次のリーダーを開発するとは
このことを考察するにあたって、私には苦い経験があります。
6年程前、弊社でマネージャー2年目だった私は、経営陣の一人から、こう言われました。
「今城さんの次のリーダーは誰なの? 私たちは、もう表舞台ではないんだよ。次のリーダーを開発して、彼ら・彼女らが表舞台に立ってこれからの会社をつくっていけるようにしていこうよ」
ようやく仕事に手応えを感じ、成長を実感していた矢先の投げかけに面食らってしまい、その時は「はい…」としか返答できませんでしたが、後でそのことについて考えれば考えるほど狼狽したり、怒りがこみあげてきました。
「私はむしろこれから表舞台に出ようとしているのに、何を言っているんだ」
「表舞台から降りるのはあなたの方で、私ではない!」
「一度も脚光を浴びずに、私のビジネスパーソン人生は終幕か…」
こうした負の感情がさく裂し、しばらくの間は気持ちを立て直すことができませんでした。それ以来、リーダーの定義としてのこのフレーズからは何となく距離を置いてきた自分がいます。
表舞台を後進に譲るという意味で世代交代をしていくことは、ビジネスだけではなくスポーツや芸能など様々な世界でも見ることができます。その現場で起こっているのは、「まだまだ自分はできる」という感情と、「次の世代に明け渡していくべきだ」という理性の衝突であり、私が苛まれたのもまさにこうした生々しい現実でした。
その後、私がかろうじて取り組もうとしたことは、自我を抑え、全体を考えて行動できる視座と成熟さを身に纏っていくことでしたが、不快感は晴れず体現していくことはとても困難でした。
次のリーダーを開発するとはそもそも表舞台から降りて「座を明け渡す」ようなものなのでしょうか。
座を明け渡すとなると、先ほどの「自分はまだやれる」という思いの他に、自分の基準から他者を見て、次を担うのにふさわしいのかという評価の目線で見てしまいがちです。そうなるとますます自分の方が…という気持ちが頭をもたげてきて悪循環に陥ります。
次のリーダーを開発するというときに、この「ふさわしいのは誰か?」という問いから抜け出す必要があるように思います。
想いをつないでいく連鎖
この夏公開された『劇場版 鬼滅の刃』の最新作は、歴代1位のヒットを記録した前作を上回る勢いで絶好調です。
『鬼滅の刃』は、人の生命を奪い不老不死の力を持つ鬼と人間(鬼殺隊)との千年にわたる争いの物語です。不老不死である鬼に対して、寿命のある人間。鬼は「自らの存在が永遠である」と言いますが、それに対し戦う鬼殺隊のリーダーが言い放った印象的な言葉があります。
「永遠というのは人の想いだ 人の想いこそが永遠であり 不滅なんだよ」
大切な人の命を鬼に奪われた人間が、自分以外の人に同じ経験をさせないという想いで鬼に立ち向かい、攻撃を受けて犠牲が出ても次から次へと戦う存在が立ち現れます。そうした人々の想いが重なり受け継がれて、千年という長き因縁に終止符が打たれようとしていきます。
ここでの人の想いとは、「大切な人が理不尽に命を脅かされることなく幸せに暮らし天寿を全うする世界を実現する。そのために脅威の根源である鬼を断つ」ということです。
想いが共鳴し、自ら立ち上がる人が現れる。圧倒的な困難に対して、一人や一世代では実現できなくても、次の存在が継承して実現に迫っていく。
自分一人や自分がいる間では成し得ないことを夢に見て、本気で実現しようとするところはこの物語に限らず、私たちの社会や会社にも大いに当てはまります。そこに他者が進んで参加したいという想いが宿り、その想いをつないでいくところに立ち上がろうとする人の連鎖が生まれる、すなわち次のリーダーの開発が結果として起こると解釈できます。
リーダーの定義の一つが、なぜ次のリーダーを開発している、ということなのか?という問いから出発しましたが、多くの人が共感する世界を描いて発信し、他者が進んでそこに参加したいという想いを喚起させることはリーダーの行動そのものであると思います。その影響力が、結果として次のリーダーを生み出すということはとても自然に思えてきます。
舞台そのものを創る
このように考えると、約6年前に私が問われたことは、
「表舞台から身を引いて、後進に譲りなさいと」いうことではなく、「あなたが実現したいことに周囲の人が自ら進んで参加して、それを担うリーダーになりたいとまで思う、そんなビジョンとしてあなたが思い描いていることは一体何なのか? それを、実現するためにどんなことに取り組むのか?」ということだったのではないかと思い至ります。
あなたが表舞台から降りる/降りないではない、舞台そのものを創るような仕事をしよう、ということなのではないかと。
そう考えると、当時感じていた不快感は全くありません。
あなたが本気で実現したいのはどのような世界ですか?
それは誰のリーダーシップを喚起するでしょうか?
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考文献】
吾峠呼世晴(著)『鬼滅の刃』 16巻 第137話、 2019年、 集英社
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。