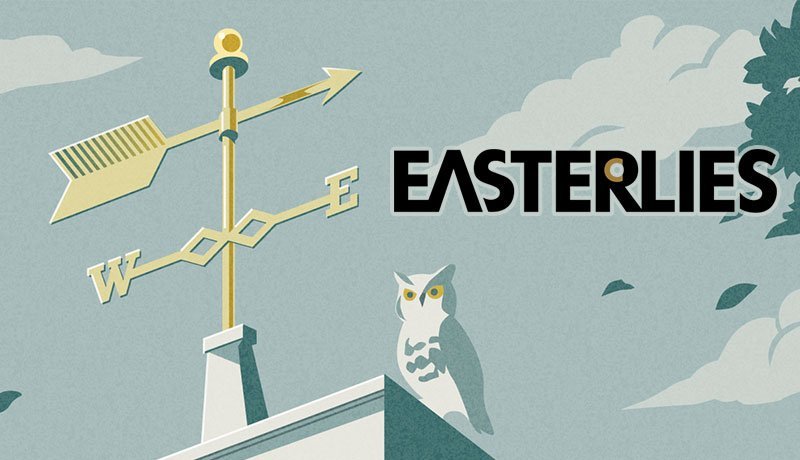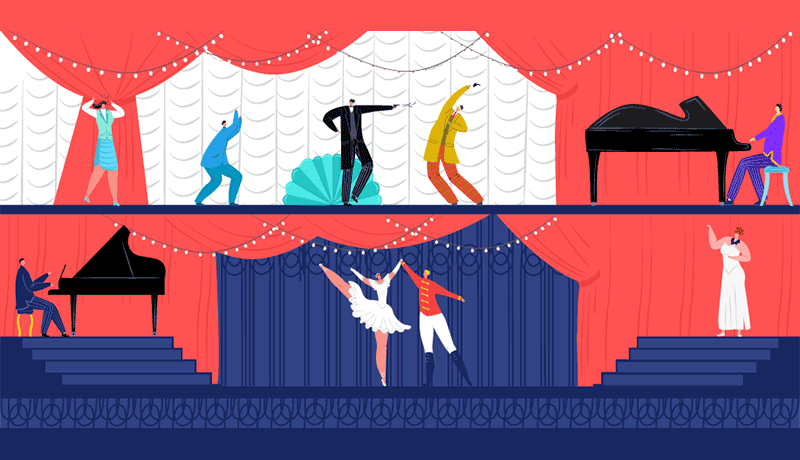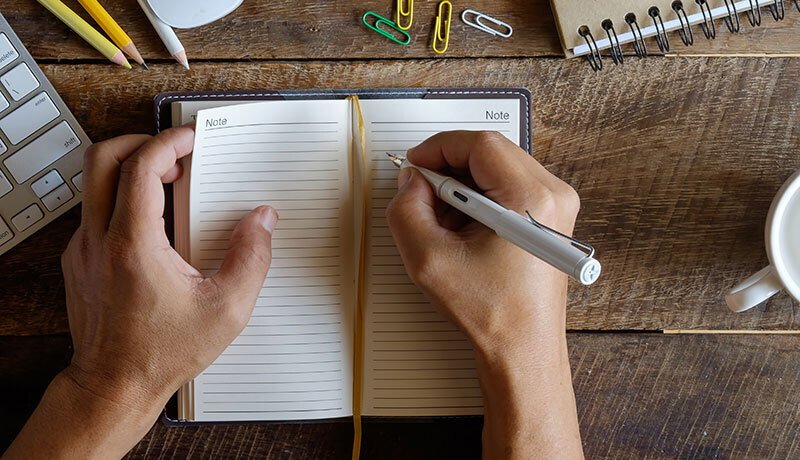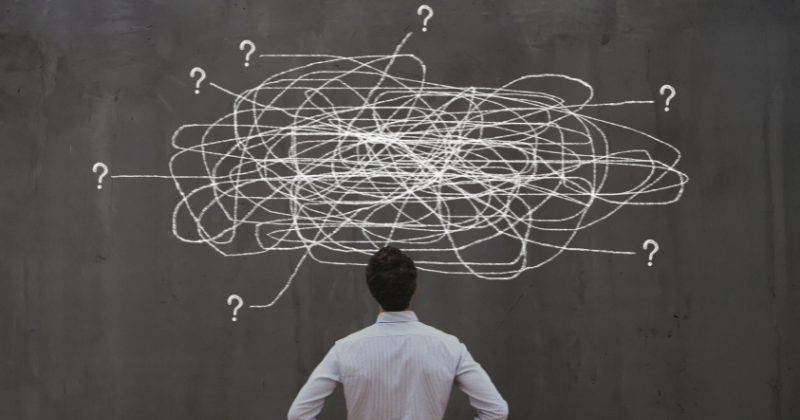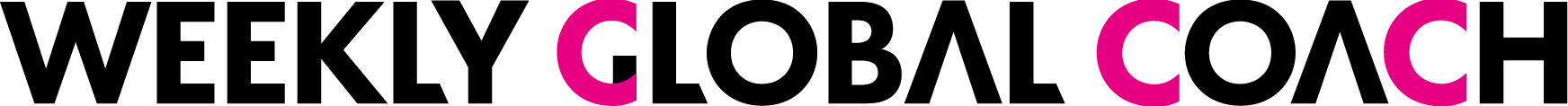Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
包みを解く

「開発って、なんだか上から目線じゃない!?」
コーチ・エィで大事にしている言葉に「開発」があります。入社当時、「うちは人材育成という言葉は使わないから。人材開発ね」と強めに念押しされた記憶が今でも鮮明に残っています。ですが、そのとき、実は違和感がありました。というのも、前職では、一流の技術者を育成するとか、最高のおもてなしができる社員を育てるなど、人材育成に全社一丸となって相当の力を注いでいたのです。
加えて、私が「開発」という言葉から浮かべたのは、更地にブルドーザーが入ってきて、大規模な工事が始まり、知らないうちに素敵な建物ができあがるイメージ。それを人になぞらえるなら、まっさらな状態の新入社員に、ずかずかと上司や人事、外部業者があれこれと関与して、理想の社員に仕立て上げる、というようなもの。
今思えば、そんな単純な想像をしてしまったからなのですが、正直そのときはしっくりこなかったばかりか、「開発って、なんだか上から目線じゃない?」とさえ思いました。
そのときから、「人の開発に携わるとはどういうことなのか?」をずっと考え続けています。
開発とは「包みを解く」こと
そんな中、「開発する(=develop)」の語源は、古フランス語の「desveloper」だということを知りました。これは「dis-(離れる)」と「veloper(包む)」から成り、「包みを解く」「隠れていたものを現す」という意味があります。覆っていたものを取り除いて、隠れていた何かに光を当てるような意味合いでしょうか。
この語源に触れたときに、私の中で「開発」が、コーチ・エィで大事にしているもうひとつの言葉と結びつきました。
それは、「人と組織の可能性をひらく」。
私はこの言葉がとても好きです。無限の可能性がつまっている宝箱を開けたときのような高揚感。コーチングでクライアントの小さな変化を目にしたときにも同じものを感じます。
「開発」とは、まさにこの「可能性をひらく」こと。外から何かを押し込むことではなく、その人の内にすでに備わっているものを見出し、表に現していくプロセスなのだと思うようになりました。
本人もまだ気づいていない可能性をひらく
組織が期待する人材像に沿って教え育てること(=育成)も重要ですが、開発には「その人自身が持つ可能性を協働で発見し、継続的にひらいていく」というニュアンスがあります。
そうした開発を組織の中で実現する機会としては、たとえば、下記のようなものが挙げられます。
①学習や経験を通じた開発
- 負荷をかけないと達成できないようなアサインメントからの成功体験や学習体験
- 他部署、異業種、海外などでの新たな経験が、未知の強みや関心に気づく契機になる
②自己認識や自己理解を深めることによる開発
- 対話を通じて、自分の価値観や前提、意味づけ、動機の源泉を言語化・可視化し、自分がどうありたいかを見出す
- 自分は何がしたいのか、自分の意見や考えを安心して相手にさらけ出す中で、眠っていた発想や才能に気づく
③組織としての開発
- 失敗を責めず、プロセスを評価し、挑戦を応援・歓迎する文化をつくることで、新しい可能性に踏み出しやすい環境になる
- 多様なキャリアパス、ロールモデルの提示により、複数の成功の形を目にすることで本人の視野が広がる
これらが組み合わさり、「まだ自分でも気づいていない可能性」がひらくきっかけとなるのです。そして、それを促進するのが「コーチング」です。
可能性をひらいたリーダーたち
ある金融機関のリーダーは、「失敗はありえない。失敗したら将来のキャリアはない。」という暗黙の組織文化を危惧し、乗っているレールから逸脱することを避けてきました。しかし、コーチング・セッションで「この会社をもっとグローバルな組織に変えたいと思って自分は入社したんだ」と思い出し、諦めていた海外支店勤務を直訴。現在は、アジア全域を統括するポジションで活躍されています。
また、あるリーダーは、対話を重ねる中で、利益優先の経営方針によって研究開発のプロジェクト本数が少なくなり、研究開発者のモチベーションも下がっていることを重大な課題だと位置づけるようになりました。そこで、本部長として、研究開発チームによる全社的なコンベンションを企画実行。また、研究開発・販売・マーケティングとの合同ミーティングで、若手を中心とした発表の機会を作りました。その結果、新たなプロジェクトが複数立ち上がり、その中から新事業も生まれました。
ある企業の役員には、「人として合わない」と思い悩むほど苦手な役員がいました。その役員との関係性が重要な事業計画のスピード感を鈍らせていたのですが、そのことをなかなか自分自身で認められませんでした。しかし、「今最も成し遂げたいことは何か」という問いに向き合ったことで関係性改善を決断。まずは相手のことを理解しようと自分から話しかけ、食事にも誘ったりするうちに、対話する相手として互いに欠かせない存在となりました。今では、週3回、朝30分の対話を行い、問題が発生したら真っ先に相談する関係性になりました。
これらはいずれもリーダーたちの壮大な物語ですが、可能性をひらく営みは、日々のちょっとした出来事の中でも起こっています。
小さな可能性がひらかれるとき
今回、このテーマでコラムを書くにあたり、私自身の可能性がひらかれた経験にもいろいろと思いをめぐらせました。たぶん、その最初の経験は、小学校1年生のとき。みんなの前で、担任の先生から急に「逆上がりをやってみなさい。あなたはきっと上手にできるから。」と言われたときです。
それまで私は人見知りかつ引っ込み思案で、おとなしく目立たない子供でした。ところが、初めて挑戦した逆上がりは思いがけず大成功し、みんなに拍手されたことで何かが覚醒。そこからメキメキと強めのリーダーシップを発揮するキャラクターに変貌し、今に至ります。担任の先生は、私の小さな可能性をひらいてくれた恩人です。
可能性をひらく営みは、特別な場面だけに起こるものではありません。
新しい知識を得たとき。
苦手だと思っていたことに挑戦したとき。
仲間から思いがけないフィードバックを受けたとき。
そんな小さな変化が、内側に眠っていた力を目覚めさせていくのです。
昨日できなかったことが、今日できるようになる。
その積み重ねで私たちの可能性はひらかれていくのですから。
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。