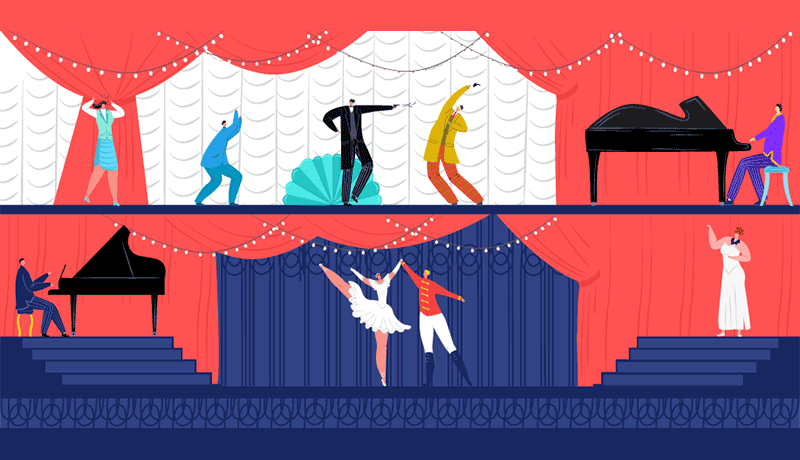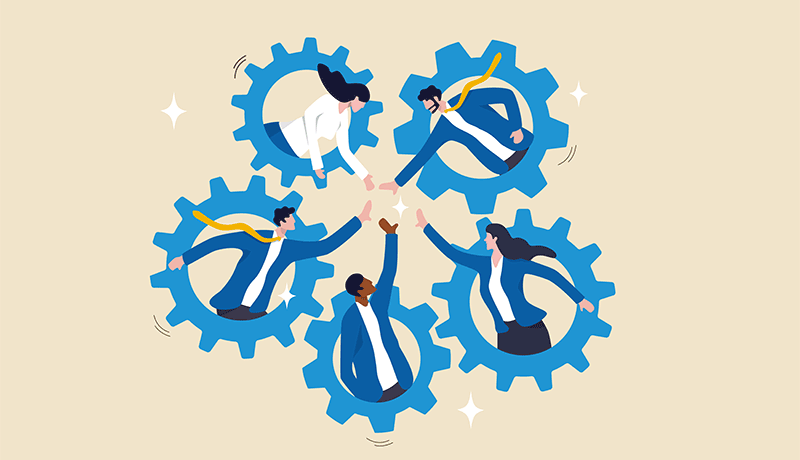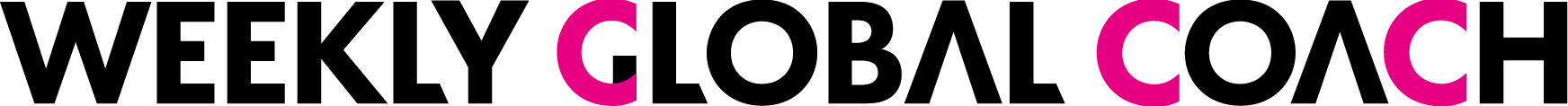Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
「曖昧さ耐性」というリーダーの知性 ― 発達する組織を育むコーチングの力
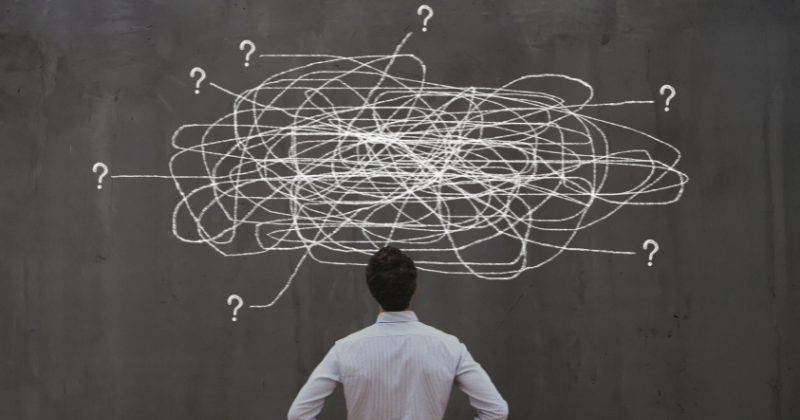
仕事や組織の中で、私たちは日々、スピードと成果を求められます。限られた時間の中で結論を出し、方向を示すためには、シンプルでわかりやすい説明が欠かせません。
そのため、「結論を早く出せる人」や「説明が明快な人」が信頼を獲得しやすくなるのは自然なことです。特に、複雑で不確実な今の時代、物事を整理し、伝え、理解させる力は重要です。社会全体でも、「わかりやすさ」は大切な価値として定着しています。しかし一方で、わかりやすさを追い求めすぎるあまり、曖昧さを受け止める力が少しずつ失われているようにも感じます。
わかりやすさの陰に潜むリスク
長らくトップダウン型マネジメントで成長を続けてきたX社は、市場環境の変化に伴い戦略を転換し、その実行のために社員のマインドセット変容を試みました。それまでの「指示・統制」から、「対話・協働」へ。
しかし、それは容易ではありませんでした。背景には、長い時間をかけて築かれてきた「明確な指示と迅速な実行」という成功パターンがありました。上司の指示や説明が明快であるほど、部下は無意識のうちに正解を求めるようになります。すると上司はさらにわかりやすい指示・説明をすることで応えようとする。そうして互いに“明快さ”を前提とした関係を続ける中で、曖昧な状況や未知の課題に向き合い考える力が育ちにくくなっていたのです。
わかりやすい答えを出すことを良しとする文化が残っている限り、思考の変化は起こりにくい。まさに、「わかりやすさの陰で、曖昧さに向き合う力が削がれる」という現象が現実に起きていました。
曖昧さ耐性 ― 不確実性を受け止める知性
ビジネス課題の多くは、複数の要因が絡み合い、唯一の「正解」が存在しません。心理学やリーダーシップ研究では、このような状況に対応する力を「曖昧さ耐性(Tolerance of Ambiguity)」と呼びます。そして、この「曖昧さ耐性」が高い人ほど、ストレスを感じにくく、多面的な情報を扱い、創造的に問題を再定義する傾向があることが示されています。
私が関わるリーダーの中にも、曖昧な状況を受け入れることで、チームの思考を深める方がいます。彼らは、結論を急がず、問いを残すことで、メンバーが自ら考える余白をつくり出すのです。彼らは不確実な状況を「決められない」とは捉えません。むしろ、「まだ決めない」ことで思考を耕し、チーム全体の知性を引き出している。それは優柔不断ではなく、状況と相手を深く理解しようとする知的誠実さの表れだと感じます。
これまで数多くのハーバード・ビジネス・レビューの記事や、様々な文献を読んできて、私は「曖昧さの中でこそ、リーダーの価値観が問われる。明確な答えを持つことよりも、揺らぎの中で一貫性を保つことが信頼を生む」と解釈しています。曖昧さにとどまる力とは、まさにこの「揺らぎの中の一貫性」を支える知性なのです。
曖昧さが組織にもたらす“余白”
矛盾と曖昧さに満ちた現実の中でこそ、新しい価値は生まれます。たとえば営業現場では、これまでも、顧客と会社の間にある葛藤を抱えながら、どちらか一方の「正しさ」に偏らず、両者を生かす第三の解を模索してきたのではないでしょうか。曖昧さと矛盾を抱えながら前に進む力。それはすでに多くの現場で育まれている“実践知”です。
一方、社内に目を向けると、「わかりやすい方針」「短期成果の徹底」「個人評価の明確化」。こうした明快さ・わかりやすさを重んじる文化の中で、迅速な判断力は磨かれてきました。そうした中で、「短期成果が出れば続ける、出なければ止める」「自分で全てを仕切るか、他者に任せるか」といった二項的な思考が広がり、白でも黒でもない領域を扱う機会が減っている…。
もしそうだとすれば、それは組織にとって“可能性の余白”がまだ多く残されているということです。曖昧さを共有しながらそこに意味を見出していく力が育まれるとき、組織の知性はより豊かになっていくのだと思います。
曖昧さの実践を支えるコーチング
「わかりやすさ」の実践は容易に想像できます。たとえば、明快な資料、迅速な意思決定、端的なメッセージ。
一方、「曖昧さ」の実践となると、何をどうすればよいのか、途端にわかりにくくなります。「とどまる」「考える」と言われても、日常の行動に置き換えることが難しいのです。
まさにここに、コーチングが機能します。コーチングは、対話の中で新しい問いと意味を共に生み出すプロセスだからです。そしてそれは、個人の行動変容だけではなく、関係性そして組織の変容ももたらします。
リーダーが「答えを出す人」にとどまらず、そうした対話を通して「組織が成長していくための問いを育む人」として機能するとき、チームの中に“考え続ける文化”が育ちます。曖昧さに耐える力は、そのような日常の対話とコーチングによって鍛えられていくのです。
発達する組織の鍵は「曖昧さ耐性」にある
もちろん、わかりやすさは統率のためにこれからも必要です。わかりやすく語り、同時にわかりきれないことを共に考える。常に結論を急ぐだけでなく、時には問いを残す。そこにこそ、対話と成長の余白が生まれます。
組織の未来を決めるのは、そのように曖昧さの中に成長の可能性を問い続けるリーダーとチームの「関係の成熟度」ではないでしょうか。
私は、わかりやすさを追い求める力と、曖昧さにとどまる勇気を併せ持つリーダーが増えていくことが、これからの日本企業の進化につながると感じています。
わかりやすさは、人を動かす力
曖昧さは、人と共に考える力。
この二つを行き来できるとき、リーダーの言葉には、思考を促す静けさと温かみが宿るのだと思います。
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。