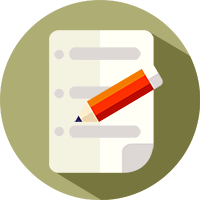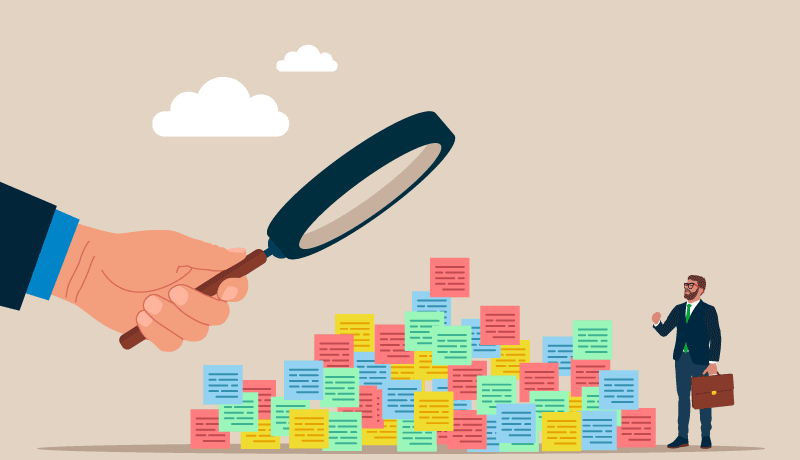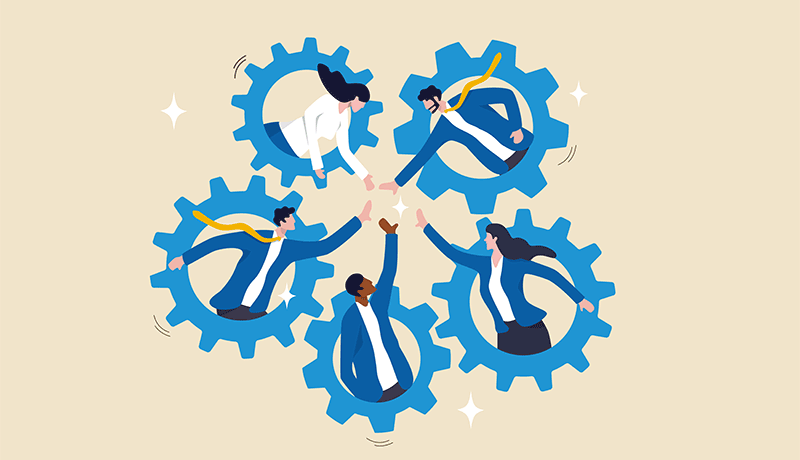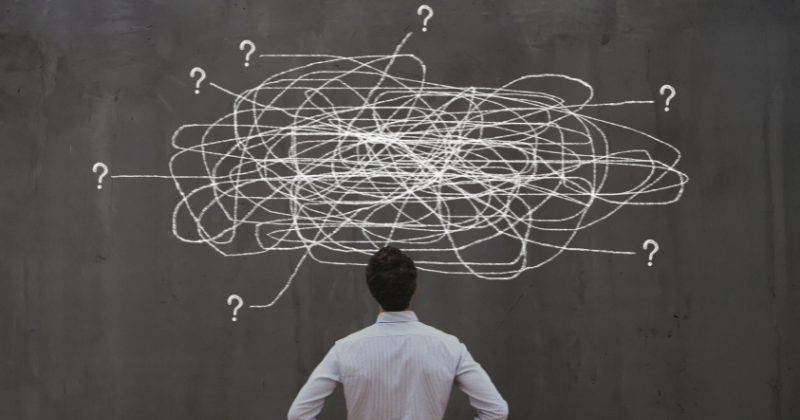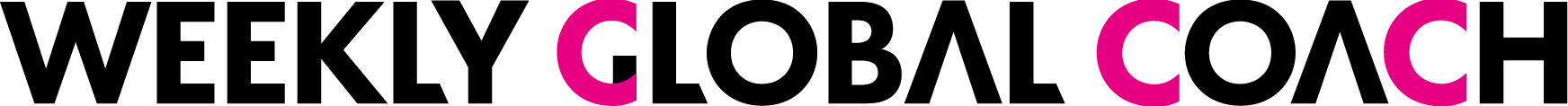Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
なぜ人は「その言葉」に惹きつけられるのか
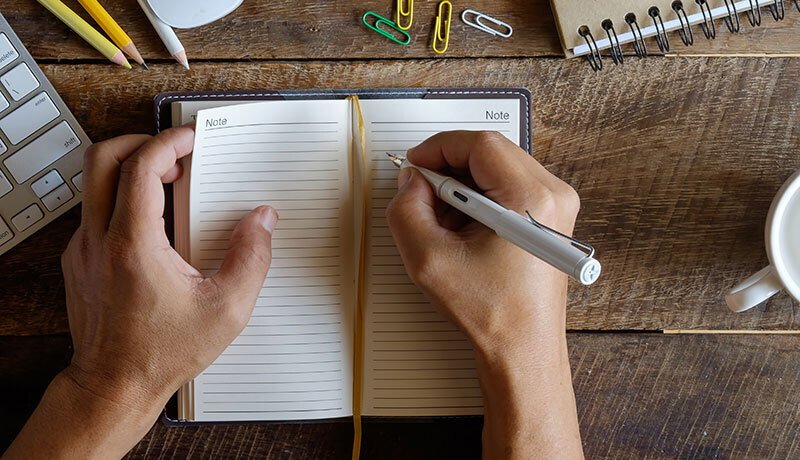
「経営者には人徳が必要だ。その人徳を伸ばすには、エグゼクティブ・コーチングは最適だと思う」
私がプロジェクトをご一緒している企業の経営者と対話している際、その方が発した言葉です。私自身もその言葉にとても共感し、また我々のサービスに対しても誇りを感じました。
会社に戻り、その話を同僚にしたところ、こう言われました。
「なぜ大山さんはその『人徳』という言葉にそこまで惹きつけられたんだろう? 正直、私は全く心が反応しないんだよね」
同じ言葉でも、ある人には胸に刺さり、ある人には心に残らずスルーされることがあります。あるいは、今まで全く心に残らなかった言葉が、表現を変えると心に残る、ということもあります。
結局のところ、人が「その言葉」に惹きつけられるというのはどういうことなのでしょうか?
問題意識だけではない
最近私はこのことについて、数人のクライアントと話しました。
クライアントAさんとの対話では「自分の問題意識と重なっている時なのではないですか?」とAさんが言いました。
「問題意識というのは、課題だけではなくて、興味があるとか、関心が高いとか、そういうことも含めてですが」
このようなケースは、皆さんも体験があり、納得感があるのではないでしょうか。たとえば私自身がコーチという仕事を選び学習を始めた頃は、電車の中で他の乗客が「コーチング」を話題にしていると、急にその人のことが気になりました。コーチングの世界ではこれを「レセプター」といって、いわば「聞く耳」が立っているような状態です。
でも、今回私が「人徳」という言葉に心が動いたのは、これだけでは説明が難しい気がしました。たとえば「経営者にはリーダーシップが必要だよね」と言われたら、もちろん「ノー」とは思いませんし、私もリーダーシップには非常に関心が高いわけですが「経営者には人徳が必要だよね」と言われた時ほど惹きつけられるわけではないからです。
そこでAさんと対話を続け、私はAさんに問いかけました。
「たとえば、昔は沢木耕太郎さんの『深夜特急』を読んで、急に会社を辞めて自分探しの一人旅に行っちゃうような人がいましたよね? でもその多くは、元々そういったことをしたいと思っていたわけではないんだと思うんです。あるいは、Aさんは小学生の頃にラグビーを始めましたが、それまでラグビーに興味があったわけでも、何か運動をしたいと思っていたわけでもなかったそうですね。しかし『これだ』と閃いてのめり込み、そこからずっとラグビーと接していますよね? こういうことは問題意識とか興味関心だけでは説明しきれないと思うのですが、どうなのでしょうか?」
Aさんはしばらく考えて答えました。
「うーん、確かにそうですね。でも思い返すと、そのベースには、何かを変えたいとか、現在に物足りなさを感じているとか、そういうことがあった気がしますね。その時に出会ったものに『これだ!』と触発されということはあったと思います」
価値観が変わる時、言葉への感度が高くなる
人は皆、自分なりの価値観の枠組みがあります。価値観は、人生の体験を通じて形成されますが、その価値観の枠組みは環境やその人の成長に起因する部分が大きいため、大人になってからも変化しうるものです。
特に、自分の枠組みを変えようと自分自身に働きかけている時は、言葉による外的刺激の影響は受けやすいのかもしれません。
私が「人徳」という言葉に共感したのは、自分自身が価値観の枠組みを扱うエグゼクティブコーチという仕事をしていることに加え、年齢や立場を重ねていく中で、自分自身の枠組みを変化させたい、パラダイムシフトしたいと感じているタイミングだったということがあるように思います。
また、それまでの自分は「リーダーシップ」という言葉を意識して自身のケイパビリティを高めてきましたが、どこか成長の頭打ちを感じ、自分の成長テーマのコアを言い表せていない感覚がありました。そんな時「人徳」という言葉は、より抽象的な概念ではあるけれども、思わず「自分にはそれがどの程度備わっているのだろうか?」と考え続けたくなる言葉だったのです。
「パラダイムシフト」という言葉の生みの親となった、20世紀の科学者であり哲学者であったトマス・クーンは「科学者がパラダイム転換を受け入れるとき、それは論理ではなく『見る世界が変わった』ことによる」と言いました。
これはつまり、価値観の枠組みに置き換えると「ある言葉が響くのは、その人のパラダイムが変わる瞬間にいるから」と言えると思います。自分自身が変化の過程に身を置いている時は、変化が起きやすいのではないでしょうか。
探求の旅へ
私自身「なぜその言葉に惹きつけられるのか」については探求の旅の中にいます。ただ、よくよく考えてみれば、自分のまわりの世界は「惹きつけられる言葉や表現」と「そうではないもの」で満ち溢れています。もっともっと、多くのパターンがありそうですし、いろいろな背景、メカニズムがある気がします。
私は「自分が惹きつけられる言葉」に出会った時には、ひとまずその言葉をメモしておき、立ち止まってみようと思います。その時の自分自身の変化点を知ることにつながり、自身が大事にしていることや(重要なステークホルダーが)変化するタイミングを知ることもできるような気がしています。
同時にこんなことも思いました。リーダーとしてメッセージを発信する側になった時を考えると、単に「自分が大事にしたい言葉」を発信するだけでなく、その言葉を大事にする意味、自身のパラダイムシフト、価値観の変化、そういったことに言及することで、少しでも自分の発する言葉が受け手に響きやすくなるかもしれない、と。
あなたにとって「ある言葉」に惹きつけられる時はどんな時ですか?
その時のあなたは、何を変えたかったのでしょうか?
そんな探求の旅へ、一緒に出てみませんか?
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考文献】
トマス・クーン(著)、青木薫(訳)、『科学革命の構造 新版』、みすず書房、2023年
沢木耕太郎(著)、『深夜特急』、新潮社
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。