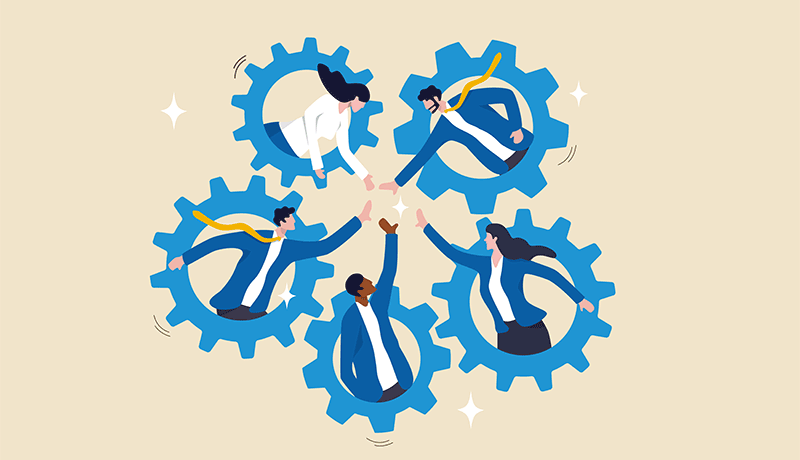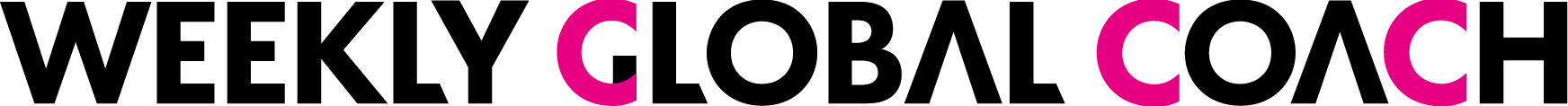Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
飾りじゃないのよチームは

今年の初め、胃に希少がんが見つかりました。
2人に1人はがんになる時代と言われているものの、予兆のない突然の告知は大きな動揺をもたらしました。幸い早期発見だったため、すぐに手術をすることになりましたが、その手術は「腹腔鏡・内視鏡合同手術」と呼ばれ、消化器内科と消化器外科の医師がコラボレーションして実施するとのこと。
日頃、経営者やリーダーの方々と接し「組織の変革をいかに実現するか」というテーマに向き合っている私にとっては、その「コラボレーション」という言葉にとても興味を掻き立てられました。手術は無事に成功したものの、全身麻酔のため手術室で繰り広げられた生のコミュニケーションを聞けなかったのは残念です。きっとそこには私の認識を超えるようなコラボレーティブなコミュニケーションがあったに違いないと想像しています。
さて、そんな「コラボレーション」ですが、ビジネスパーソンのみなさんにとってはどれだけ馴染みのあるキーワードでしょうか。
コラボレーションとは何か
私たちは「コラボレーション」という言葉を、日常のさまざまな場面で耳にします。「コラボ商品」「コラボイベント」「コラボ楽曲」など、多様な形で使われており、辞書には「異なる分野の人や団体が協力して制作すること」とあります。協業や合作、共創とも訳され、新しいアイディアや価値、意味を創ることを目的としています。
エグゼクティブ・コーチングをしていると、社長の悩みの多くは業績やKPIよりもむしろ「人」。特に、一番身近なはずの「経営チーム」についてです。
以下は、私のクライアントの言葉ですが、違う人から同じような内容を聞くことも珍しくありません。
- 経営会議では誰も反対しない。建前会議になっていて、腹の中でどう思ってるのか、本当は良く分からない。
- 仲が悪いわけじゃない。でも”一緒に”やっているところを見たことがない。
- 役員は”いい人”ばかりで、”迷惑かけるから”という遠慮が、お互いに言葉をかけたり連携し合う行動にストップをかけている。
社長は役員に対して、役員は部長に対して、マネージャーはチームメンバーに対して、そして、社員は上司たちに対して「もっと協力したらいいのに」ときっと感じています。組織が大きくなると、立場や責任、利害関係が複雑に絡み合い、協力体制を築くことが難しい場面が増えてきます。特に、自組織の成功に向けて舵を取り、確かな実績のあるハイパフォーマー集団である経営チームは、最もコラボレーションの難しいチームかもしれません。
チームワークとコラボレーション
先日、とある企業の役員の方に、自社の経営チームの関係性を伺うと「私たちは同じ釜の飯を食ってきて、同じ価値観を共有しています。コミュニケーションに課題はありません」と自信たっぷりにお話しされました。実は、役員層の方と面談をすると、こういったお話はよく出てきます。でも、ビジネスモデルの変革を迫られ、社員のマインドセットの変化を求められている状況の中で「同じ」であることは本当に大丈夫なのでしょうか。
目標を達成するために同じ価値観で一致団結し協力しあうことをチームワークというならば、コラボレーションは、協力の先にイノベーションや新しい視点、アイディアを得ることを目指す在り方です。辞書にあった「異なる分野の人や団体が協力して制作すること」に立ち返ってみれば、参画者がみな”異なっている”ことがコラボレーションの前提です。
当たり障りのない協調的な会話ではなく、違いを認め合いぶつかり合いながらも新たな価値を共創する対話こそが、コラボレーションを促進します。もちろん「違い」を認識しつつそのままコミュニケーションをするのは、たやすいことではありません。エゴやプライドが邪魔もしますし、対立は決して居心地がいいものではありません。対決すれば自組織のために勝たないとメンツがつぶれます。
“対決して勝つ”のではなく、”対立を恐れない”
本来、役員同士のコミュニケーションの目的は、同質化を前提とした暗黙の了解を創ることでもなければ、お互いの勝ち負けをはっきりさせることでもありません。役員同士がコミュニケーションをとる目的は、いかに協力関係を築けるか、そして、いかにお互いから学び、組織全体の学習につなげていくかにあります。
ところが、実際の経営会議は、報告だけ、当たり障りのない協調、あるいはディベートで満たされていないでしょうか?
どうしても私たちのコミュニケーションは二極化になりがちです。どちらが正しいか間違っているか、勝ち負け、上か下か、とコミュニケーションを使って、自分の立場を相手に定義させようと必死です。二極化の世界にいると、どちらか一方に決めつけることに意識が向きます。そして、相手を受け入れることに苦慮します。そうなってしまうと、今ある以上のものを生み出すことは難しくなります。
実は、私自身も今、同僚の執行役員といかにコラボレーティブな関係を築けるか挑戦の真っ最中です。今年度のスタート時、自分の役割が変わりました。自分への期待、ミッション、目標を実現するために、これまでとは違う考え方や動き方が求められているように感じながらも、上手く掴めないままいた私は、同僚たちを誘い自分の思いを共有しました。
「我々各々がこれまでと同じことをやっていたら同じ結果しか生まれない。エゴとプライドは脇に置き、協力しあわない?忖度・遠慮・回りくどさも一切なしで、一緒に毎日前進したい」
同僚たちも、仕事の障害になっていること、次の商談の懸念、来週の気がかり…と、周囲に相談したいことをたくさん抱えていました。もしも、一つひとつをコラボレーションして前進させていくことができたら、仕事のクオリティが早いスピードで上がっていくであろうことが、みなすぐにイメージできました。
そして、その日以来、私たちは毎朝短いミーティングを始めました。「1か月続けてみて、価値があると思ったら継続しよう」とスタートしたその場は、今や無くてはならないものになりました。実際に、一緒に手掛ける案件が生まれたり、スタックして動かなかったプロジェクトが動き出したり、プライドを脇に置いて役員同士でロールプレイをしたり、様々な共創が生まれています。
コラボレーションに向けた重要な問い
コラボレーションに重要なのは「何のために?」「誰と?」です。「何を」「どうやるか」よりも「誰と」が先。何をどうやるかはまだ分からないけれど、この人とだったらきっと面白いものが生まれるに違いないと思う相手は誰でしょうか。
あなたは、今、誰とコラボレーションしてみたいですか?
あなたがわくわくする相手は誰ですか?
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。