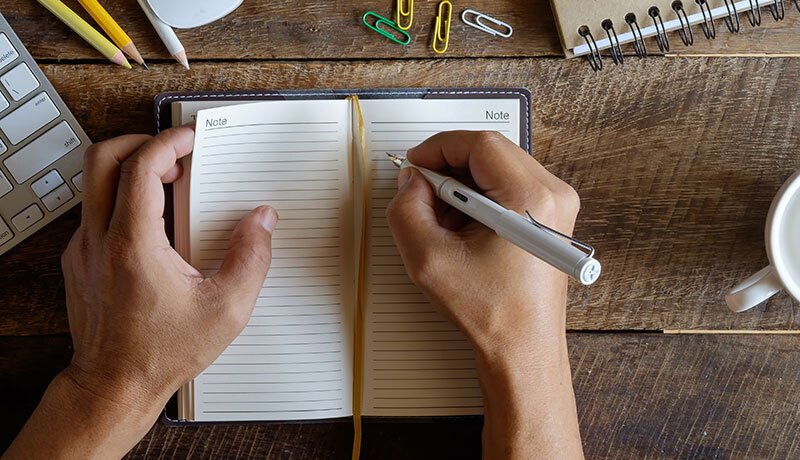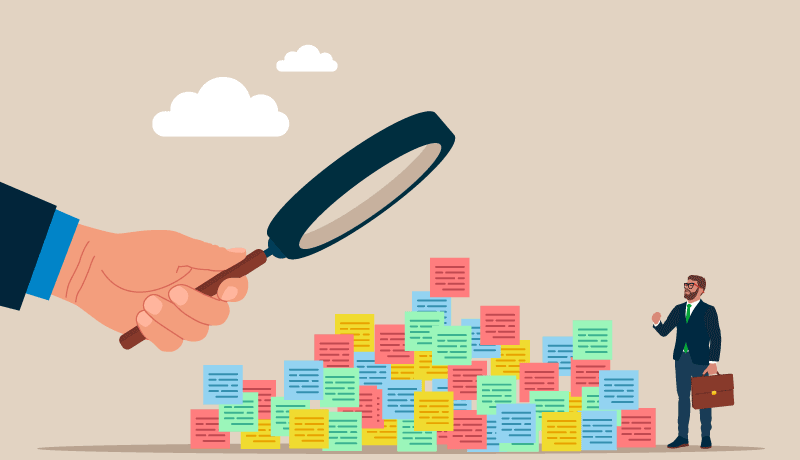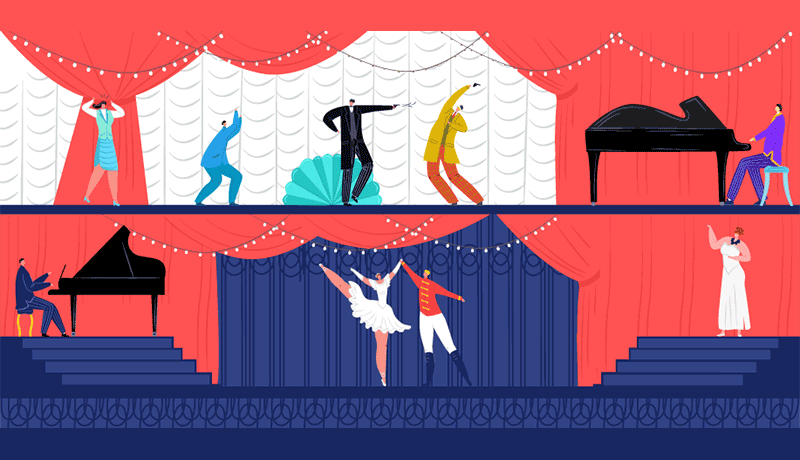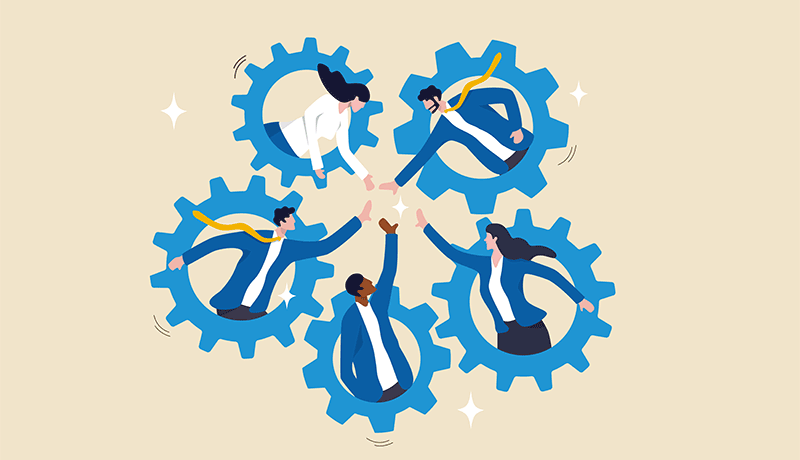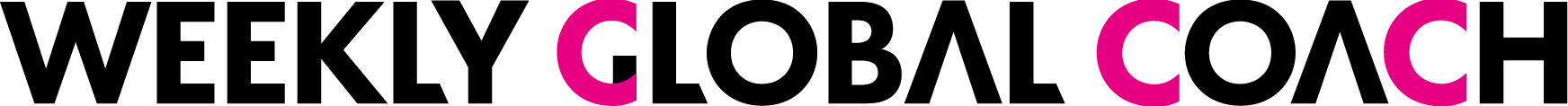Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
敗戦の乗り越え方

日本のプロ野球も、アメリカのメジャーリーグベースボールも、いよいよ今シーズンの大詰めを迎えようとしています。
日本ではクライマックスシリーズ、アメリカではプレーオフですが、両地において共通しているのは、どうも初戦に負けた多くのチームが、その後挽回することができず、敗退してしまっているということです。エンジェルス、カブス、阪神、そして我が巨人。
こうして見ると、チームが負けたときに、いかに選手の気持ちを切り替えさせ、次の試合に臨ませるかということが、非常に大事な監督やコーチの役割であるということがよくわかります。
先日、オーストラリアでラグビーのコーチングを学ばれたという方と知り合いました。聞くと、彼が学んだコーチングでは、試合に負けた時、どのタイミングで選手にポジティブな言葉をかけるかということが、ちゃんと指導要項の中に入っていたそうです。そのくらい敗戦をどう処理するかということは大事なことであるわけです。
いくつかの事例をもとに考察すると、敗戦を乗り越えさせ、次の機会に良いパフォーマンスを発揮させるには、大きく2つのことが大切になります。
まず1つは、敗戦を完了させること。要するに引きずらせないということですね。
何か失敗をしたとき、どんな形で人はそれを心理的に「完了させる」かというと、そこから何かを「学習した」という実感を持ったときであるようです。大方の場合は、敗戦後しばらく経って、「ああ、あの敗戦のお陰で自分はこれを学んだな」との認識が生まれ、やっとその敗戦が完了します。しかし、優秀な監督やコーチは、試合後すぐさま学習を顕在化させ、敗戦を完了させることができます。
早稲田大学ラグビー部を5年連続リーグ優勝に導いた現サントリー監督の清宮克幸さんが、その著書の中で書いています。
清宮さんが早稲田に就任して1年目、夏の練習試合で、目標としてきた関東学院に大差で負けました。その時、自分達がやってきたことが全く結果に結びついていないと、意気消沈する部員を前に、清宮さんは言い放った。
「今日の結果はわかっていた。全ておれの予想通りだった。この差を秋のシーズンまでに埋めていくのがおれの仕事だ。これでわれわれは、本当のスタートラインに立つことができたのだ」
つまり、この試合によって、われわれは差を学習することができたし、今後何をすべきかを知ることができた、そう言明したわけです。この清宮さんの発言で、学生たちは一気に明るさを取り戻し、モチベーション高く練習に励めたとのことです。
こちらが伝えるのでも、メンバーに考えさせるのでもいいでしょう。まずは、敗戦から何を学んだのかを明確にし、心理的に完了させる。
2つ目は、「負けた後の次の試合」への意識を過剰に高めないことです。
負けると、どうしても次の試合で勝とうとする意識が強くなり、余分なプレッシャーを持つことになります(我がジャイアンツはそれで負けたような......)。プレッシャーが高すぎると最高のパフォーマンスを発揮させることができません。オプティマルプレッシャー(最適のプレッシャー)レベルに下げる必要があります。それには、「負けた後の試合のさらに次」を意識させることです。
例えば、小さい子どもに「5円玉を机の上に立ててごらん」と言うと、なかなか立てることができません。ところが、「5円玉を立てて、その後に真ん中の穴につまようじを立ててごらん」という指示に変えると、多くの子どもが、5円玉を立てるところまではできてしまいます。つまり、「次」を意識することで、今向かい合っている状況に対するプレッシャーがやわらぐわけです。
これを実践したのが、ロッテのバレンタイン監督です。
ロッテは日本ハムとのクライマックスシリーズ第3戦で敗戦を喫し、1勝2敗となりました。3敗すればシリーズ敗退です。
第4戦、今日負ければ終わりという日に、バレンタイン監督は、その日の試合のことには全く言及させずに、勝った場合に練習日となる次の日に、どんな練習をするかばかりを話したそうです。まさに「つまようじ」戦略ですね。
これによって、ロッテの選手は、過剰に「今日」を意識しなくてよくなりました。そして、はつらつとしたプレーで、第4戦を日本ハムに快勝しました。
この敗戦の乗り越え方は、仕事でも使えそうです。
仕事で部下が「負けた」とき、まずはその敗戦から何を学習したかを明確にし、敗戦を完了させる。そして、次の勝負のときには、さらにその次を意識させ、オプティマルプレッシャーが生まれるように調節をかける。こんな風に適用できるかもしれません。
原監督に教えてあげたかった。
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。