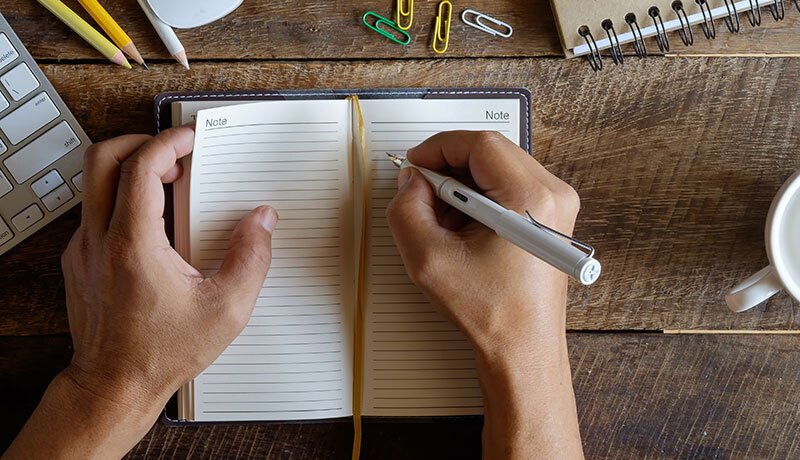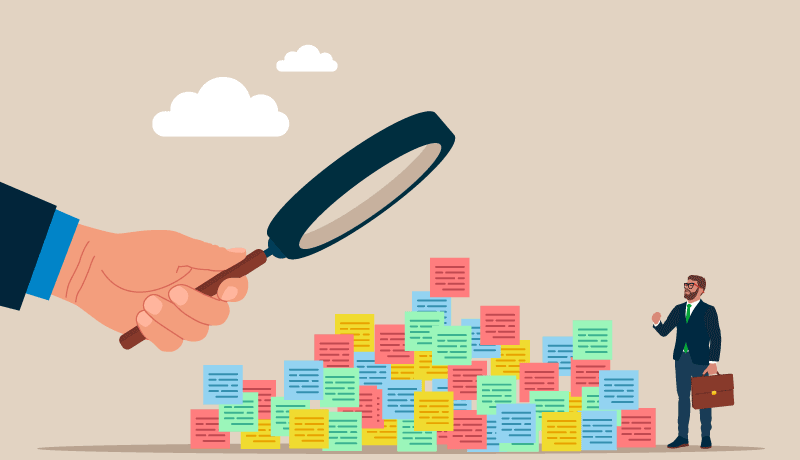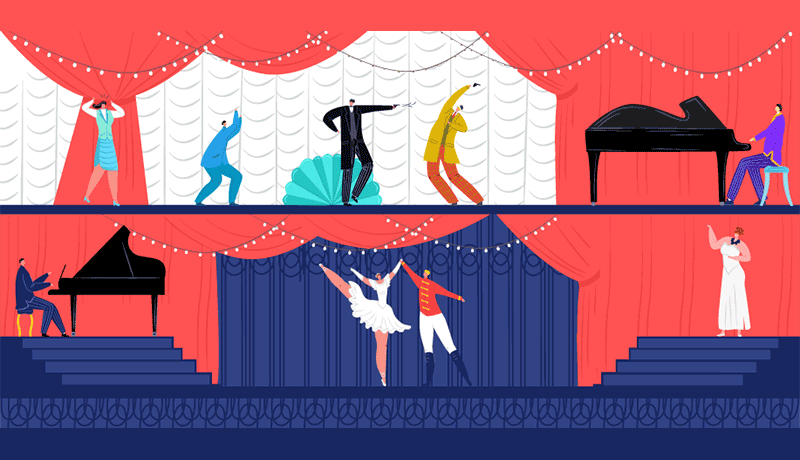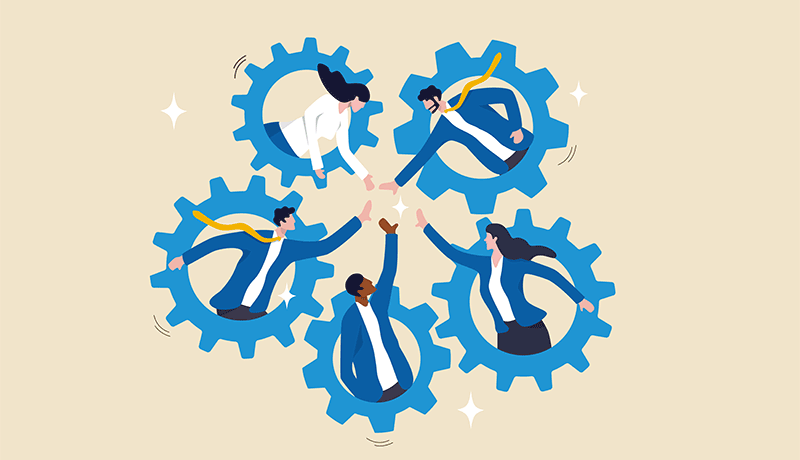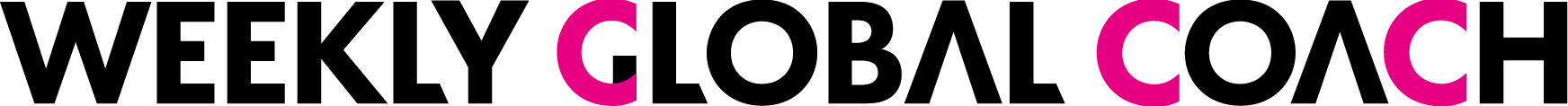Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
自発性に火をつける

ある企業のマネージャーTさんが、上司に業務改善の報告をしました。
現場スタッフによる小さな改善の積み重ね。それによって、これまで何年も達成されなかった不良率低減の目標が達成され、年間に換算すれば、約1,500万円の経費削減につながる。
この話を聞いた私は、早稲田大学ラグビー蹴球部の元監督である清宮克幸氏が、以前お話しされていたことを思い出しました。
清宮氏は試合中の選手をビデオに撮って、試合後、選手一人ひとりに、「前の試合よりタックルの回数が1回多かった」「今度は1回少なかった」と、フィードバックするのだそうです。
もし、15人の選手が、1回ずつタックルを増やせば、チームとしては15回相手を倒せる。それがとても大切なのだ、と。
小さな変化の積み重ねこそが、大きな変化を生む。
実際、Tさんの現場で起こったことも「小さな変化の連続」でした。しかも、それは結果として、1,500万円ものコスト削減をもたらしました。
そこに至る取り組みとは、どのようなものだったのでしょうか。Tさんに詳しく伺ってみました。
**************************************************
Tさんが、コーチングを実践し始めたのは、3ヶ月前のこと。きっかけは、取引先の営業担当者からコーチングの話を聞いたことでした。
職場のコミュニケーションを活性化させ、製品の不良率低下に全員で取り組むことで、会社へのクレーム減少に応用できるのではないか、とTさんは思い立ったそうです。
そこから、Tさんの部下や社内メンバーへの関わり方に、早速変化が生まれます。
・コーチングのフロー(進め方)を書いた手作りカードを部下全員に手渡して、フローに沿ったコーチングを忠実に実践した
・目標達成をテーマに、毎日たとえ5分でも、部下とこまめに関わるようにした
・コーチングの中で出てきた部下自らの目標を、会社の公式目標として認定した
・上長はもちろん、関係部署の部課長らに、部下の取り組みを話し、協力を仰いだ
また、Tさんは、実践の合間にコーチから受けた、次のようなフィードバックを意識して取り組んだそうです。
・部下の話に耳を傾けていることを伝えるため、話をし終わってから5秒待ってから自分の話をする
・部下の話を先回りして想像したり、言葉を勝手に言い変えたりしない
・一般的な問いかけではなく、部下それぞれの状況や目標に合わせた問いかけに変える
・毎回毎回、目標達成の進捗確認を必ずする
こうした関わりにより、部下たちに変化が生まれ、徐々に業務改善の報告が上がってくるようになったそうです。
Tさんは、次のような改善項目を上司に報告しました。
-------------------------------------------------------------
・担当者自身の口から、「会社が示している目標0.5%ではなく、0.3%まで不良率の低減ができるのではないかと思っている。実はそれを実現したいんです」という言葉が出てきた。
・部や課を越えて、製造ラインのメンバーと定期的にミーティングを開催するようになった。
・別の課のメンバーとのミーティングの中で、「模造紙に不良率のグラフを書き、貼り出す」というアイデアが生まれて、早速実行した。その模造紙の前を通る両課のスタッフが、原因や改善アイデアを各々書き込むようになり、双方の考えが、見える化できるようになった。
・会社から与えられていた既存のチェック表の点検項目だけでなく、これまでチェックしていなかった点検箇所を新たな項目に加えて日々点検するようになった。
・品質に影響するライン上の不備が見つかったときは、これを写真に撮り、製造ラインメンバーに共有することで、改善策をみんなで考えるようになった。
etc...。
-------------------------------------------------------------
しかし、この報告を受けた上司は、「そんなのは仕事なんだから、当たり前だろ?」と、一蹴したそうです。
確かに、経験のある上司から見ればこのような業務改善はやって当たり前だ、といえるのかもしれません。
しかし、Tさんはこう言います。
「明らかに、以前と違うのです。事実として、何年も達成できなかった目標が、たった3ヶ月間で達成しました。では、今までと何が違ったのか。それは、会社や僕ら上司から言われるままに行動していた部下たちに対して、継続的な問いかけを行うことによって、『やってみたい』『してみたい』、そして、『できるのではないか』と、彼らの自発性に火がついたこと。それが、部下、同僚、上司、他部署へと連鎖していったのだと思います」
**************************************************
華麗なトライの背景には、選手一人ひとりの、見えないかもしれないくらいの、ほんの少しの頑張りや工夫が必ず潜んでいます。それは、言われてできることではなく、一人ひとりの自発性という力によって支えられているのだと思います。
それは決して、「当たり前のこと」ではありません。
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。