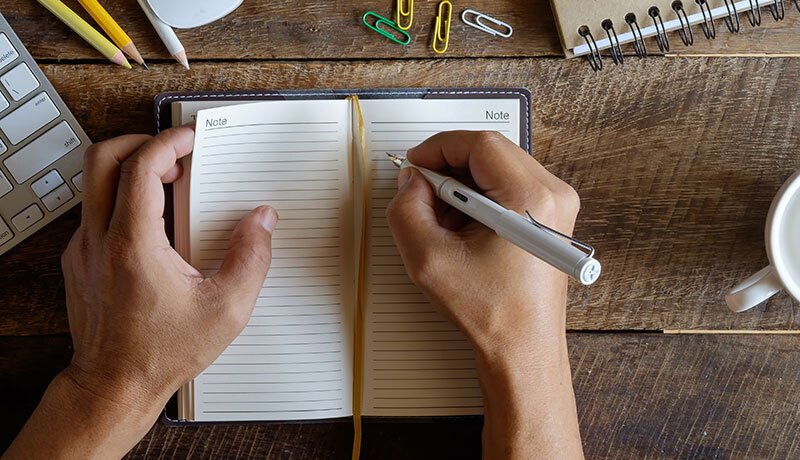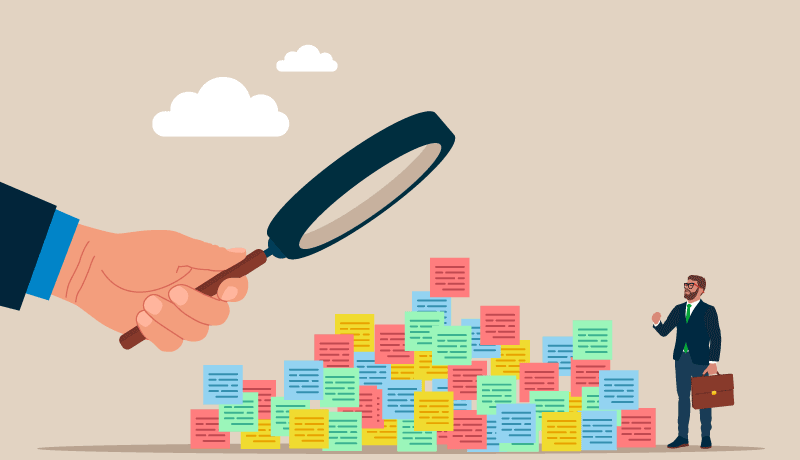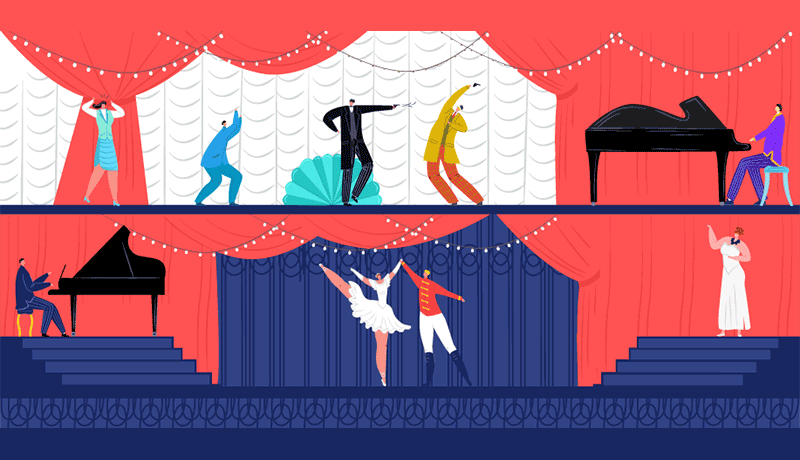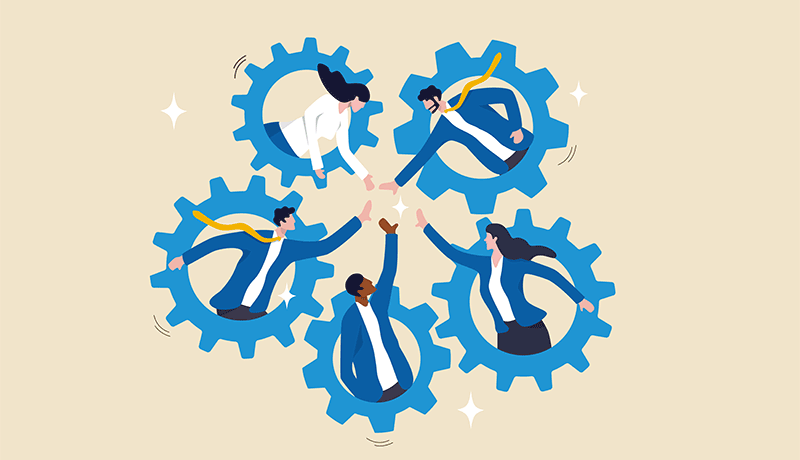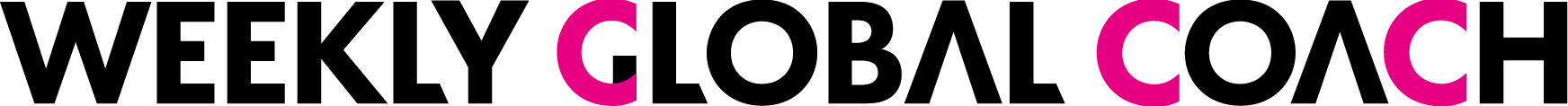Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
リーダーが忘れてはならないこと
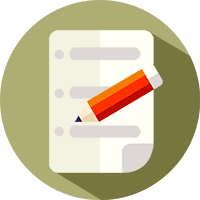
2011年11月09日

とあるリーダーが、ご自身の組織のことについて、こう嘆いていました。
「うちの会社は和気あいあいとして雰囲気もいい。しかし、うわべでは会社の方針に従っているように見えるが、実のところ付き合い程度の努力しかしない。そして、あいかわらず好きなように行動をしている......」
良く見かけませんか、こういう組織? 一見穏やかですが、あらゆる手を使って公然と組織の方針に反対する、面従腹背の勢力がいる組織。
ブース・アレン・ハミルトンのレポート(※)では、このような不健全な組織のことを「受動攻撃型」と呼んでいて、世界各国約3万人に対する調査では、こうした組織は全体の4分の1以上の27%にも及んでいたといいます。
また、別のリーダーはこう語ります。
「いまの変化の速い時代では、その変化に柔軟に、スピーディーに対応しないといけないのに、うちの社員はまったくその速さについていけていないんだ。こうしたときは、即、動くしかない。にもかかわらず、頭を引っ込めて動きを止めてしまっている奴もいる。本当に情けない......。なぜ、そのような組織になってしまうのだろうか」
このお二人のリーダーとお話をしていると、まるで自分自身が被害者のようなスタンスに立っていますが、実は、その方ご自身がその事態を引き起こしている張本人であることも少なくありません。そして、ほとんどのリーダーは自分が張本人であることに気づいていません。
この場合、まさに、「自分自身が被害者である」というスタンスから、「目の前の組織で起きている事態を引き起こしているのは自分である」ことにコンフロント(直面)し、「自分次第で、この事態はどのようにも変えられるんだ」というスタンスへのシフトが必要とされています。
私たちは、そのシフトを実現させる方法の一つとして、コーチングの前後に、「リーダーが引き起こしたい組織のダイナミズムが、現場で理想どおりに動いているのか」を調査して、それをフィードバックさせていただいています。
では、前述の「受動攻撃型」といわれる組織では、現場の方々はどのような想いを抱いているのでしょうか。
現場の方々へのアンケートやインタビューなどを通じて、「組織で何が起きているのか」「リーダーはどのように思われているのか」などが見えてきます。そのうちのいくつかを抜粋します。
●「結局、様子を見てから動いたほうが得、と感じている」
~いったん決まった方針における結果が出るのを待たずに、次の方針を出してしまうリーダーの場合~
このリーダーは朝令暮改が信条で、「変化の激しい時代では、その変化に応じて、やり方も柔軟に変化をしていかなくてはいけない」と、朝言ったことを夕方には撤回することが多かった。部下からすると、いったん従いはじめても、すぐに撤回されるケースがあまりにも多いため、「今回もまたしばらくすると変わるに決まっているから、しばらく様子をみよう」といった受け身の姿勢につながっていた。結果的に、即行動してみよう、という職場風土は失われていた。
●「結局、自分たちは任されていない、と感じている」
~部下に任せているようで、任せていないリーダーの場合~
ある商品開発を任されていた部下は、その分野を立ち上げ、かつ知識でも実績でも一番であるリーダーから、うるさく介入されていた。仮に一度決まったことでも、そのリーダーの突然の思いつきでひっくり返される、という事態が何度となく繰り返されていた。
また、介入したリーダーの意見が色濃く反映した商品が、市場から受け入れられずに失敗に終わっていたにもかかわらず、その責任を問われることもなく、誰もそれを追求することもできなかった。
その結果、任された部下からすると、結局、自分はどの範囲で意思決定権を持っているのかがわからなくなり、主体性を失ってしまっていた。
●「責任の所在があいまいで、まさか自分がやるとは思っていなかった」~仕事を思いつきで振ってくるリーダーの場合~
リーダーからは、オフィスで話をしたついでに、思いついたように仕事を振られるので、その仕事がなぜ自分に振られるのかが、本人も周りもわからない。
実はその職場では、どこまでが自分の責任で、どこからが同僚の責任なのかが、ほとんどだれも把握できていなかった。しかも、リーダーも振ったことを忘れてしまっていた。
結果的に、この職場では、最後まで責任をもって遂行しようとするマインドは消え去っていた。
●「目標達成に対するコミットが薄れていく」
~仕事を追加することはあっても、止めることのないリーダーの場合~
このリーダーは、資源は無限にあるかのごとく、自分が思いついたことを怒涛のように部下に指示をしていた。また、すべてのことを最重要課題のような勢いで仕事をさせていた。部下からすると、混乱し、力も拡散し、どの仕事も中途半端になってしまう。
その結果、このリーダーのもとでは、どの部下も目標達成したためしがなく、この職場からは、そもそもの目標達成に対するコミットは失われていった。そして、そもそも目標自体にも、誰も信頼を置けなくなった。
●「組織体制がコロコロと変わることによって、育成マインドも薄れていった」
~とにかく組織をいじるのが好きなリーダーの場合~
このリーダーのもとでは、半期に1回の組織改編は当たり前。社員からは、コロコロとその場しのぎで組織を変えている、というふうに見られていた。
組織を頻度高く変えることが定着していたため、社員のマインドとしては、あまり好ましくない状態になっていた。それは、「目標達成しなくても、来月にはゼロクリアになるし」という、あたかもゲームのリセットボタンを押せばすべてが生まれ変わる、かのような感覚に社員を陥らせていた。
また、いま持っている部下も数ヶ月後には、離れる可能性もあるし、自分が部下になる可能性もあるため、じっくりと部下を育てるといったマインドも、この組織には消え去っていた。
こうした現状、みなさんの職場でも起きていませんか?
昨今、環境の変化に柔軟にスピーディーに対応していくことばかりが強調され、推奨されています。しかし、そのやり方を一歩間違えると、「やってもやらなくても、同じ」といった無力感に苛まれた組織がつくられていってしまうことも、私たちは理解しておかなくてはなりません。
リーダーは、自身が理想とする現場の状態を掲げ、常にそこに向かって組織がドライブしているか、否かをチェックする必要があります。
リーダー自身がよかれと思ってやっていることも、現場での望ましい行動を引き起こしていない場合はやり方を変えるしかありません。
そのとき、「なんで、みんな動かないんだ」という被害者のスタンスで「やり方を変える」のではなく、「そもそも、動かないのは、自分のリーダーシップの何が影響しているのか?」「自分は何を引き起こしてしまっているのか?」というスタンスから、やり方を変えていく必要があります。
リーダーは、ただ単に「やり方を変える」前に、そもそもの自分自身のスタンスを、「被害者で他責」から、「主体者で自責」へと変えることが先決かもしれません。
【参考文献】
※『組織行動論の実学』
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部 編訳
(ダイヤモンド社刊)
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。