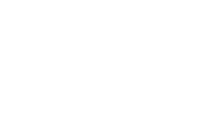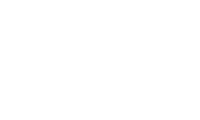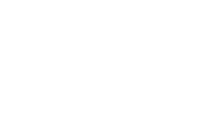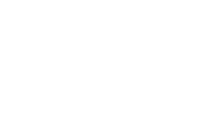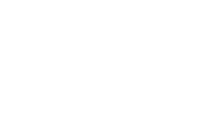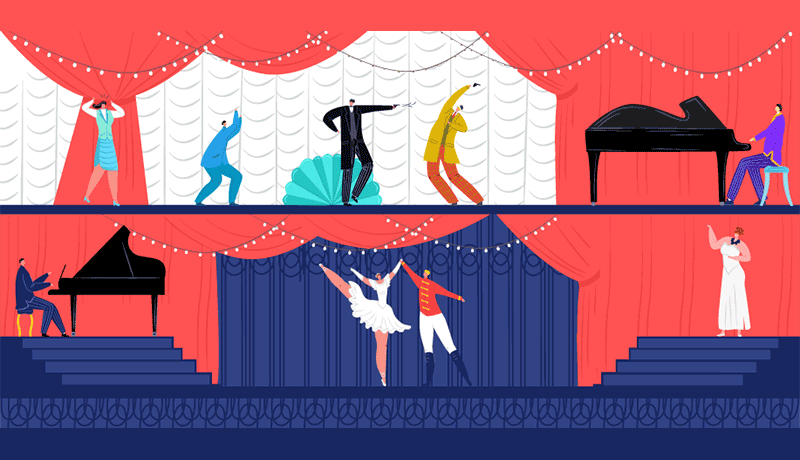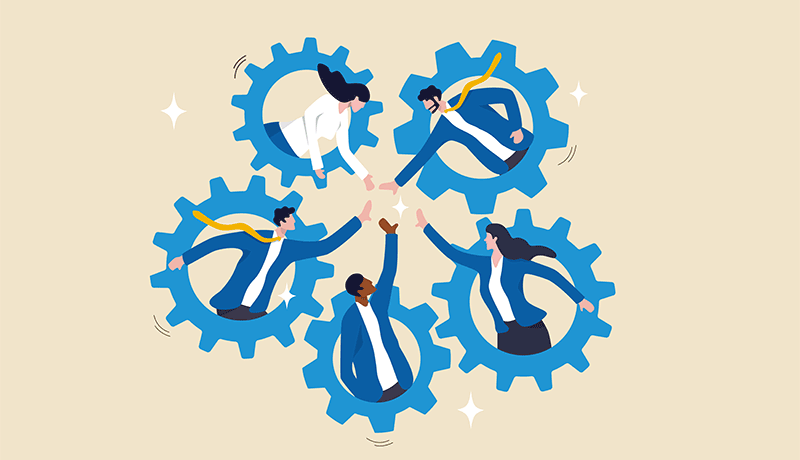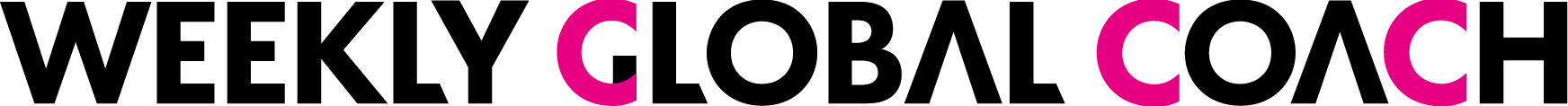Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。
なぜ、うちの「エース」は辞めてしまうのか

2017年07月12日

タフなアサインメントで、次世代リーダーの育成をしよう。
こうした意図で、期待する若手を海外赴任させたり、子会社に出向させたりするケースは年々増えているようです。
ところが、帰任後しばらくして、期待の彼/彼女から突然辞表が提出され、人事も上司もがっくり...という例も、後を絶ちません。
成長のチャンスを与え、戻ってきて、「いよいよここから!」という時に、いったい何が起こっているのでしょうか。
突然の辞表、多いのはいつ?
エグゼクティブ・コーチングの依頼が多い1つのケースとして、新しいポジション就任時というタイミングがあります。
確かに、こういった「トランジション(移行期)」に、コーチングは有効です。移行期には、本人の認識や行動様式に、必ず変化が求められます。その変化へより早く適応していくことに、コーチとの対話が役立つからです。
米国のエグゼクティブ・コーチングファーム、CoachSource社が2012年に実施した調査によると、調査に参加した企業の97%が自社の「リーダー開発」のために「コーチング」を活用しており、そのうちの42%は、「トランジション」=「職位や役割の移行」のために活用しているとしています。(※1)
ところが、冒頭のとおり、出向先・赴任先から元の組織に戻る「リ・ボーディング」のタイミングこそが、実はもっとも本人にとって「揺らぎ」の大きい時期であり、コーチが必要とされていることは、あまり知られていません。
この「リ・ボーティング」こそが、企業にとって有望な人材を失うリスクが非常に高いタイミングなのです。
エコノミスト紙は、2015年11月の記事で、以下のようなリサーチに注目しています。(※2)
スペインのIESE ビジネススクールSebastian Reiche 氏の計算によれば、10% ~ 60%の「帰任者」が、帰国後2~3年以内にその会社を辞める。その離職率は、明らかに、海外赴任をしていない社員よりも高い。
ドイツのフリードリヒ・アレクサンダー大学 のJan Sebastian Knocke 氏のレビュー論文によれば、「文化の異なる国に『融合すること』よりも、『帰還』の方が難しい、という兆候がある」という。
こういった事実に反して、「元に戻る」という一見難易度の高くないトランジションに対して、本人も周囲も十分な準備と対応がなされていないようです。
なぜ、「ビーだま・ビーすけ」は面白いのか
先日、「ピタゴラスイッチ」「だんご3兄弟」など、多くの作品でブームを巻き起こしてきたクリエイターの佐藤雅彦氏の講義を聞きました。
佐藤氏の作品を支える表現手法のひとつに、「物語性」があります。
彼は、このように説明しています。
ひとつひとつは訳の分からない事柄なのに、並べて提示すると、それを解釈するのに「ある物語」を人間はたちどころに創り上げてしまう。
この「物語をたちどころに生み出す能力」は、自分の目の前に現れた一見不可解な出来事群に対して、納得できる筋道を与える『人間に用意された生きていくための力』ではないか。(※3)
この「物語性」をうまく活用した作品のひとつが、「ビーだま・ビーすけの大冒険」です。
これは、積木や缶など、身の回りにあるもので作られた、NHK Eテレの番組「ピタゴラスイッチ」のからくり装置を、ビー玉3つが転がっていく動画です。
3分ほどのものですが、後半になるにしたがい、「ただのビー玉」たちが、さまざまな障害にぶつかりながら、からくり装置を進んでいく"大冒険"の様子を、思わず手を握り締めて、見守っている自分がいることに驚かされます。
私たちは、何でもないような事柄でも、そこに「意味」を見出し、「物語」として解釈せずにはいられない。そのことを、改めて実感できます。
実は、私たちは日常生活でも、この「物語」づくりを、休みなく繰り返しています。
「この困難は自分にとって、新しい挑戦である」
「将来やりたい仕事をやるための1ステップだ」
誰しもが、こうして自分なりの「物語」を紡ぎながら、生きているのです。
では、この「物語」と言う観点で、「リ・ボーディング」のプロセスを見直してみるとどうでしょうか。
リ・ボーディング人材の物語はどうなっているか?
チャレンジングな経験をし、学びを得て帰任した人材は、3つの理由から、強いカルチャーショックを体験する傾向があります。(※4)
1) 知らぬまに変化した自分自身のアイデンティティ
2) 元いた組織の人的ネットワークやルールなどの変化
3) 帰任後に対してポジティブな期待を抱きやすい
皮肉なことに、帰任者が赴任先にうまく適応していた度合いが高ければ高いほど、このショックは大きく、長引く傾向にあります。
ところが本人は、「元に戻る」という考えから、以前の自分の記憶を頼りに、「このように上手くいくはずだ」と楽観的な物語を予想していることが多いのです。
実際は、自分も周囲も変わってしまっていますので、予想は裏切られていきます。
その結果、周囲との関係が以前より希薄に感じられたり、以前取り組んでいた仕事が色あせて見えたりする、といった印象を多くの帰任者から聞きます。中には、「同じ会社に戻ったはずなのに、まったく違う会社に来てしまったようだ」と語る人もいます。
そして、その時にも人は、目の前で観察する事実と事実をつなげながら、なんとか自分の「物語」の続きとして解釈しようと試みています。
自分の予想や期待が次々に外れていく過程で、多くの帰任者は、だんだんと所属している組織や仕事内容に対して、「こんなはずではない」と批判的な意味づけをし始めます。
予期せぬカルチャーショックに対する、自然な防衛反応として、現状を批判せずにはいられないとも言えるでしょう。
「ここでは、自分は必要とされていないのではないか」
「自分は競争から取り残されてしまったのではないか」
「自分の経験をもっと活かせる場所が他にあるのではないか」
SNSが盛んな今、都合悪く、このようなタイミングで、多くのヘッドハンティングが声をかけてきます。物語が揺らいでいるタイミングで、「あなたにぴったりの冒険はこっちにありますよ」と聞こえてきたら、帰任者の心が動かされるのも無理はありません。
変化をつくりだす一手とは?
多くの企業では、このような事態を無力感とともに、見送っているようです。
そして、
「MBAに送らなければよかった」
「やはりエースは海外には出さないでおこう」
そんな声も聞こえてきます。
果たして、この解決方法が「チャレンジさせない」という結論で、本当に良いのでしょうか。
変化を作り出す一手として、私が検討したいことのひとつは、彼らが帰任した後、「物語」を描き続けるプロセスに、周囲がどのくらい参加しているのか、ということです。
新たな意味づけや解釈は、自分自身と、あるいは他人との「対話」を通してしか成しえません。その「対話」を、本人任せにするのか、誰が、どのくらい参加するのか、そこには選択肢があります。
面白いことに、そのプロセス次第では、見えてくる「物語」はたったひとつではありません。本人の持つ「批判的な視点」で見えなくなっている可能性には果たしてどんなものがあるでしょうか。
- 伝えられていない周囲からの期待
- 経験を活かせるチャンス
- 全く新しいミッションの可能性
- まだ手つかずの成長課題
- ここから始まる新しいキャリアステージ...
どれだけ「広い視点」でともに対話を創り出していけるか、そこにチャレンジしたいのです。
対話を通じて、ともに新たな「物語」を見出せたときに初めて、彼らの経験や視野は、会社の新しい刺激と力に繋がっていくはずです。
ますます加速するタレント獲得競争の中、会社の未来を担うリーダーたちの「リ・ボーディング」をどう成功させられるか。
今後も注目していきたいテーマのひとつです。
この記事を周りの方へシェアしませんか?
【参考資料】
※1 Kalman,F.,2014,”Special Report: Executive Education”,Media Tec Publishing Inc.
※2 " Not-so-happy returns ,Big businesses fail to make the most of employees with foreign experience" The Economist, November 7th, 2015
※3 佐藤雅彦、『考えの整頓』、暮しの手帖社、2011年
※4 Craig Storti,2001,The Art of Coming Home,Nicholas Brealey
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。