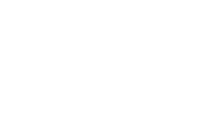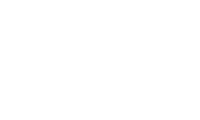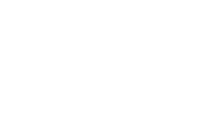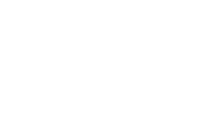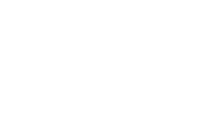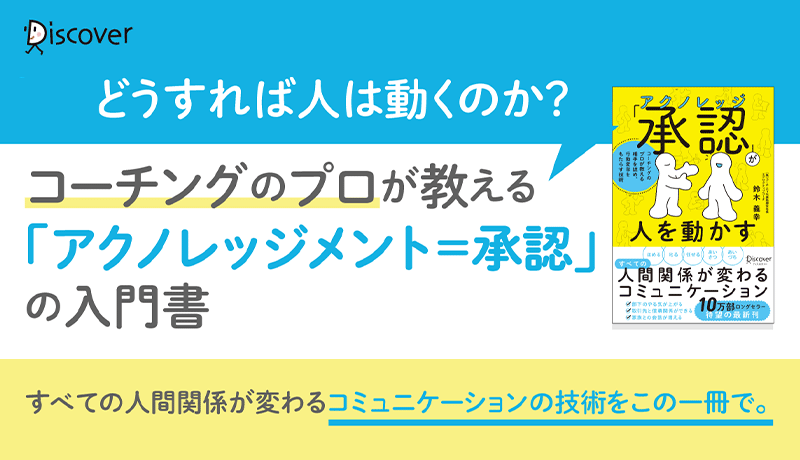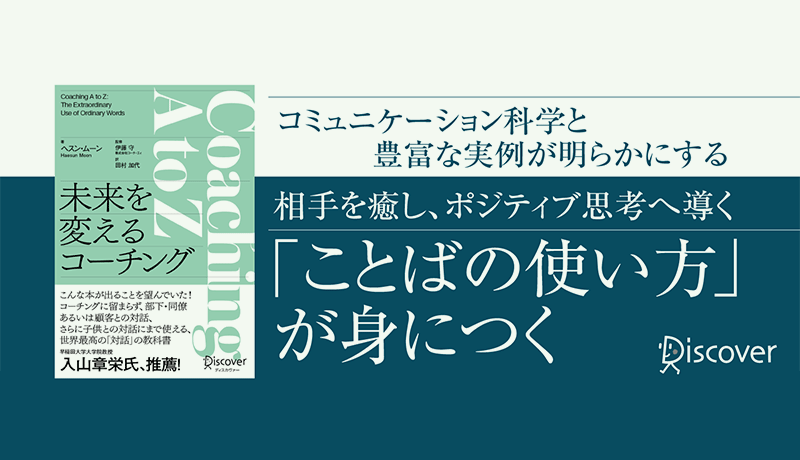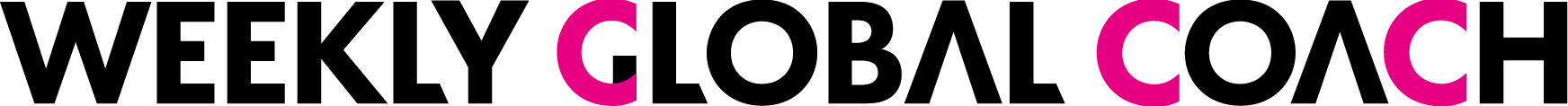Hello, Coaching! 編集部がピックアップした本の概要を、連載形式でご紹介します。
ケン・マネジメント代表 佐藤 けんいち 氏
第1回 「現在」を知るために「歴史」をさかのぼる
2017年10月16日

「逆回し」で見えてくる「現在」の本質!
現代は、これまでの自明の前提が崩れ先行きの見通しの難しい時代だ。世界全体がそうであるし、ビジネスの世界においても同様だ。こんな時代において、「現在」を知り、「未来」を考えるために、「過去」の歴史を知ることが重要視されるようになっている。ビジネスを広い文脈の中に位置づけて、重層的かつ複眼的に考える。まさに歴史を読み解くのと同じ力が「現在」を生きるビジネスパーソンには必要な能力として求められている。
本連載では、「ビジネスパーソンによるビジネスパーソンのための歴史」を皆さんにご紹介したい。
| 第1回 | 「現在」を知るために「歴史」をさかのぼる |
|---|---|
| 第2回 | トランプ大統領が誕生した裏には、どんな潮流があったのか |
| 第3回 | 今の都市型ライフスタイルは、どんな風につくられてきたのか |
| 第4回 | 都市型ライフスタイルを送る現代人特有の「2つの意識」 |
| 第5回 | 「歴史の三層構造」の視点を用いて歴史を見る必要性 |
リバースエンジニアリングの手法で歴史を読み解く
「ビジネスパーソンのための歴史」と銘打つにおいて、このリバースエンジニアリングの手法を特徴としたい。通常の歴史とは真逆の方向に歴史を見るのである。リバースエンジニアリングとは今目の前にある製品をバラバラに分解することで、その構造と機構、構成部品の詳細を知り、 「見えない設計図」を再現する行為を指す。ものづくりは基本的に「設計図」に従って製造工程を進めていく形で行われる。まずはパーツ、それを組み合わせたユニット、そしてユニットを組み合わせモジュールに組み上げて、アセンブリーによって最終製品に加工される。「リバースエンジニアリング」の発想は、上記のような通常のものづくりの真逆の方向で行われる。最終製品をバラすプロセスを通して、逆に設計図が見えてくるのである。設計図がないからこそ、分解してメカニズムを明らかにするのである。
この手法をアナロジーとして歴史に当てはめてみよう。最終製品として「現在」のいまここにあるモノは、「過去」につくられたモジュール、さらにその前に作られたユニット、さらにその前に作られたパーツにさかのぼっていくことができる。これは物理的な形をもったハードだけではなく、映像作品などのソフトについても同様だ。ソフトウェアも過去に作られたプログラムのうえに成り立っている。この手法によって、時間を「現在」から「過去」にさかのぼって、個々の要素を明らかにすることができる。それによって、現時点の最終製品である「現在」について、要素ごとに深く知ることになる。それが「リバースエンジニアリング」を用いることによって実現したいことなのだ。「現在」は、「過去」と「未来」によって規定されているのである。だが、「未来」については正確に把握することは人間には難しい。できることはまず、「逆回し」で「過去」にさかのぼっていくことだろう。
「現在」を知るために「歴史」を遡る
西欧中世史が専門の歴史学者・阿部謹也は、動物行動学が専門の生物学者・日高敏隆との対話をまとめた『新・学問のすすめ 人と人間の学び方』(阿部謹也・日高敏隆、青土社、2014年)という本の「第2章 「自分とはなにか」から始まる学問 歴史学(阿部謹也)」で、以下のような発現をしている。
歴史学というのは、一般的には過去を知ることだといわれています。しかし私はそうは思いません。歴史学というのは、現在を知るための学問です。(...中略...) 結局のところ、 「自分とはなにか」ということを中心にして、現在を知ることになるのです。自分を知ることは、まわりを知ることになりますし、それは人間そのものを知ることでもあります。非常に細かいところから、非常に広いところまで広がっていく。それが歴史学だと思ってもいいのです。(...中略...) 歴史発見のおもしろさというのは、異文化との接触と言ってもいいし、SF的なおもしろさといってもいい。歴史学には、そういう要素もあるのです。
では、「現在」を知るための「歴史」はどうあるべきなのか? 同じ本の「第3章「学び」の原点はどこにあるのか」に以下のようなやりとりがある。
阿部 教科書というのはパターンが決まっていて、歴史でいえば古代から始まっているんですよ。ぼくは、現代からさかのぼっていくような、そういう歴史を書くべきだといっているのですが。
日高 「いま現在、こうである」ということから始まって、なんでそうなっているのかというふうにしていけば、みんな興味をもちますよ。
本書では、この発想にしたがって、「いま現在」からさかのぼって、「なぜそうなっているのか」という疑問に読者みずからが気づいていくための材料を提供したいと考えている。「過去」についての認識をもつことは、「現在」に生きる人間が、いやおうなく「未来」からやってくる時間のなかで、現実的にものを考え、生きていくために不可欠であるからだ。
英国の「EU離脱」とトランプ大統領誕生
さて、「現在」からさかのぼって歴史を見ていくにあたり、まず見るべきは2016年に起きた2つの衝撃的な事件「EU離脱」と「トランプ大統領の誕生」だろう。英国が先行し、つづいて米国がそれに呼応するかのように発生した事象を、単なる偶然と片付けてしまうことができるのだろうか?
英米はアングロサクソンとしてひとくくりにされることが多い。英国は「立憲君主制」、米国は「連邦共和制」と政治形態は異なるが、共通のルーツをもつ同類の存在とみなされてきたし、彼ら自身もそう思いたがるところがあるようだ。英語や英語圏特有の思想の近さも要因としてあげられるだろう。2016年の英米それぞれ二つの政治的な動きの背景にもまた共通するものがあるといっていい。それは行き過ぎた「グローバリゼーション」への反作用とでもいうべきものだ。その反作用はそれぞれの国民投票と大統領選でテーマとなった「移民制限」に賛成の意を示す有権者が多かったことからも見ることができる。「新自由主義」のもとで自由主義を徹底すると、社会的な強者は強くなり、社会的な弱者はさらに弱くなる。「持てる者」と「持たざる者」の格差が拡大していく。2016年の両国の衝撃の背景には、こうした経済的格差拡大への反発が底流にあったと見るべきなのだ。
政治経済のエリートと、彼らが主導する「グローバリゼーション」の拒否、最後のよりどころとしての「国民国家」への回帰路線。これは「ナショナリズム」のあらわれであり、「新自由主義」へのアンチテーゼである。これを「ポピュリズム」でひとくくりにするのは正しい見方ではない。今回は特に英国の「EU離脱」について詳しく見ていきたい。
「EU離脱」の歴史
まず、英国とEUの関係について見ておこう。「第二次世界大戦」で勝利国となったものの財政的に疲弊しきった英国は、インドを中心とする海外植民地を維持できずに手放し、世界を支配した「覇権国」の地位から完全に転落していた。1958年に設立された「欧州経済共同体(EEC)」には加盟せず、1960年には対抗して英国が主導する「欧州自由貿易連合」を結成して独自路線を歩んだが、経済不振から脱することはできなかった。英国は方針転換によって、1963年にはEEC加盟を申請したが、政治経済の超大国の米国に対抗心を燃やしていた政治大国フランスが強硬に反対し、英国の加盟は実現しなかった。1971年の「ニクソンショック」や1973年の「石油ショック」などの外部環境の激変の中、ようやく「欧州共同体(EC)」は英国の加盟を認めるにいたった。1975年には「EC残留」を巡って「国民投票」を実施、2016年とは異なり、残留となった歴史もある。
サッチャー首相は、「EU加盟」には反対しなかったが、「共通通貨ユーロ」の導入には最後の最後まで強硬に反対し続けた。その結果、英ポンドをつかいつづけることになり現在にいたっている。
「ブレクジット」の開始
2016年6月の「国民投票」に示された結果を受け、英国政府は、2017年3月29日、リスボン条約第50条に基づき、EUに対する離脱通告を行い、2年間に及ぶ「EU離脱」交渉の開始を宣言した。ついに、もはや引き戻ることのできないポイント・オブ・ノーリターンを越えてしまったのである。
僅差とはいえ、国民の過半数が「EU離脱」を選択した引き金となったのは「移民問題」である。米国で始まった2008年の「リーマン・ショック」は、米国よりもむしろ欧州の経済により深刻なダメージを与えたが、現時点においても欧州経済の貧弱性は完治したと言うには程遠い。ポーランドを中心とする欧州域内からの移民が大量に英国に引き寄せられたのは、英国経済が欧州域内では相対的にパフォーマンスがよかったからでもある。「移民問題」が、英国の「EU離脱」の引き金になったのはそのためである。
歴史的に見ると、英国にとって「離脱」はけっして珍しい話ではない。日本と同様に「島国」の英国は、つねに「大陸」とは距離をおいてきた。「島国」という地政学的特性を持った国家の国民がもつ「見えざる意思」、あるいは個々の英国人のDNAに刻み込まれた「本能的行動」と呼ぶべきかもしれない。そもそもの英国の出発点も、中世以来、西欧を支配してきたカトリック世界からの「離脱」にある。16世紀のイングランド王国ヘンリー8世は、カトリック教会から「離脱」して、国家単位の教会である「国教会」を立ち上げた。みずからの離婚問題が原因であったとはいえ、結果として英国の自立を実現する出来事になったと、後世から評価されている。
「離脱」は「解体」につながりやすい
英国による「EU離脱」は、「連合」からの「離脱」である。「連合」や「連邦」からの「離脱」が、流血の事態を招かずに平和裏になされたならば、世界史においては稀有な例となる。これまでの世界史においては、「分離独立運動」のほとんどは武力衝突を招いており、流血無しで独立を獲得した国家は極めて少ない。誰かひとりのメンバーが「一抜けた」で、グループそのものが崩壊してしまうことはよくあることだ。
1776年に「独立宣言」を発表し、英国との独立戦争を戦って独立を獲得した米国だが、「連邦共和国」として出発した米国では、19世紀半ばには「連邦」からの「離脱」が危機を招いている。「南北戦争」である。米国内で、工業志向の「北部」の政策に反発する「南部」の11州が「離脱」を宣言し「南部連合」を結成したことで、「南北戦争」という米国史上最大規模の「内戦」が勃発したのだ。
また、「冷戦構造時代」には米国と対抗関係にあった大国の多民族国家ソ連もまた、「連邦」からの「離脱」の危機が迫ったことにより、最終的にソ連邦が解体し、ソ連という国家は地上から消えた。1991年のことだ。ソビエト「連邦」においても、連邦を構成する共和国が離脱することは法的には可能だったが、ソ連経済が弱体化するまでには、そういった動きが顕在化することはなかった。
英国による「EU離脱」は困難ではあっても平和裏に実現するであろうが、一般に「連合」(=「連邦」)からの「離脱」は、一筋縄ではいかないものがあるのだ。
今回はここまでとし、次回は米国へと視点を移し、トランプ米国大統領の誕生とその背景にある歴史をみていきたい。
(次回へ続く)
この記事を周りの方へシェアしませんか?
※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。